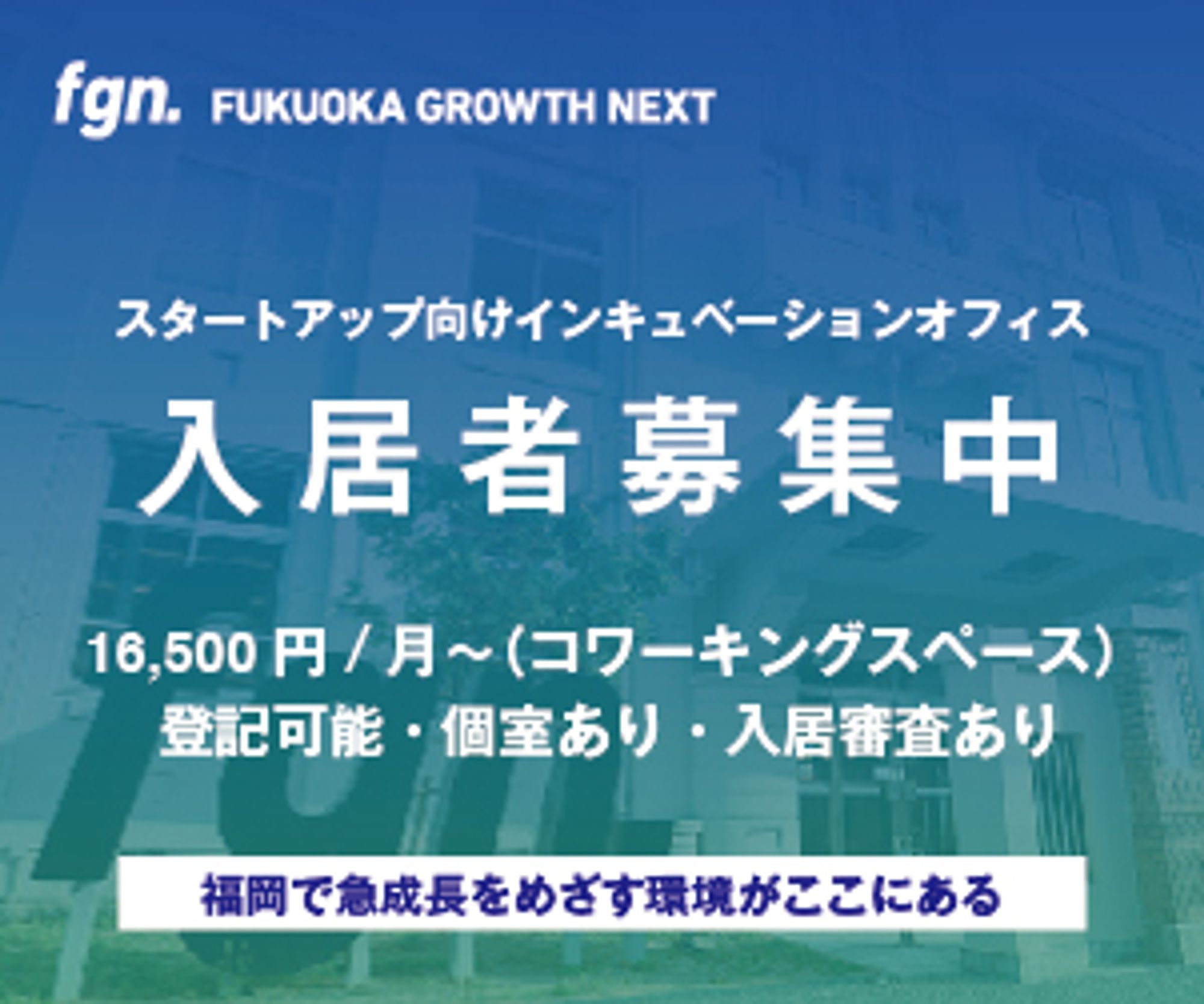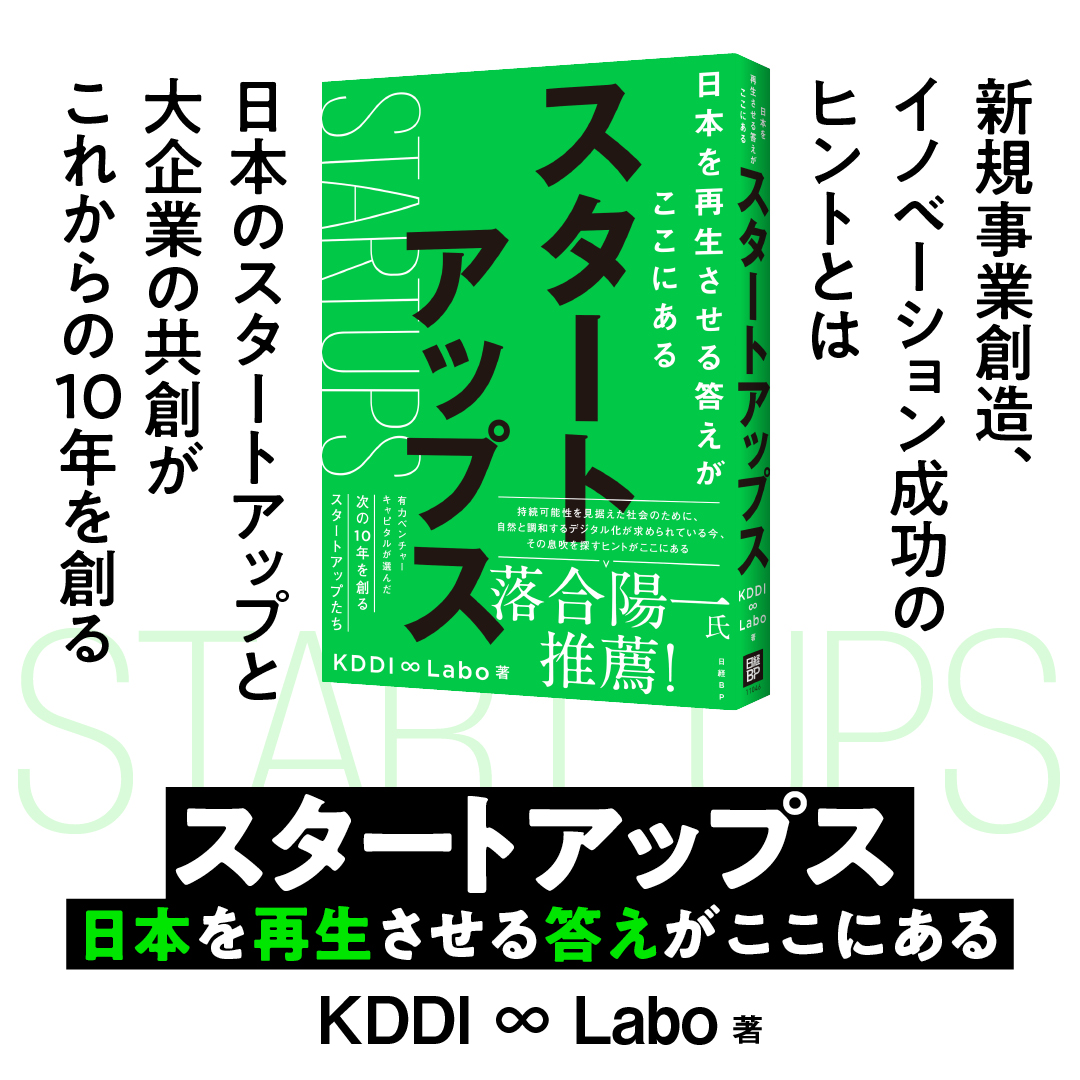脳トレゲーム「BrainWars」の勢いが止まらない。ゲーム関連でよくみかける大量の広告投下を一切使わず「自然増」でその数字を積み上げていった結果、約半年というスピードで700万ダウンロードを達成した。好調な成長の一方、やはり「ゲーム」というカテゴリの難しさ、ややもすると一発屋で終わりかねない怖さもつきまとう。
そこで私は運営するトランスリミット代表取締役の高場大樹氏に、数字の躍進や今後の展開などの疑問について、本人から話を聞くことにした。(太字の質問はすべて筆者。回答は高場氏で文中敬称は略させていただいた)
最初は教育系アプリの企画から始まった

トランスリミットとして会社を立ち上げる前、高場氏はある企画を思いつく。その内容は教育系のアプリで、現在のBrainWarsとは全く違う内容のものだったそうだ。私はある関係者からその話を聞いていたので、まずはそこからBrainWarsの成長の背景を探ることにした。
最初は教育系アプリだったとお聞きしてます。どうして教育関連に興味を持っていたのですか?
高場:皆さん小さい頃に教育を受けて大人になるじゃないですか。もちろん重要な要素だし、事業やっていくなかで人のためになることをやりたい、という考えはあったんです。
どうしてその企画をボツにしたのですか?
高場:ちょっと真面目にやりすぎたのかもしれません。私たちのチームは元々ゲームを開発してきた人間ですし、真面目にやりすぎるとやはり事業としては時間がかかりすぎる可能性が出てきたんですね。それで事業を成立させるためにも過去の経験と掛け合わせをしよう、ということでこの企画(BrainWars)になったんです。
ーー高場氏らはサイバーエージェント関連の会社でアメーバピグの海外版などに携わった経歴を持ったチームだ。ややもするとエグくなりがちなゲーム市場で若干、異彩というか変わった戦い方をしているなという印象があったのだが、最初は教育サービスをやろうとしていたのであれば、なんとなく納得がいく。スマートエデュケーションやQuipperといった部類と確かに少し似ている。

なるほど。少し他のゲーム競合の方々との違いがわかった気がします。では早速、急成長の理由についてですが、まず、これってまだ自然増のままなんですか?
高場:はい、そうですね。元々、年内(2014年)にうっすら500万ダウンロードぐらいは攻めなきゃいけないという考えはありましたが、正直、想定以上に伸びています。
いつまで広告投下無しで続けるつもりですか?
高場:まあ、いけるところまではこのままでやるつもりです。
私も過去、海外に挑戦するスタートアップを書いたりしていたのですが、正直、どれもここまでの急成長はなかったように思います。どうでしょう、高場さんが考える理由は?
高場:やはり日本向けだけに作らなかったことでしょうか。デザインやルール、全てにおいて世界向けに仕様を作ったことです。

具体的に教えてください。例えばデザイン箇所ではどういう工夫がありましたか?
高場:例えば色ですね。自分が緑で相手がピンクといった対比をさせたりしてます。(表示されたブロックを逆からタッチしていくゲームを見せながら)「逆」という意味をピンクを使って表現してます。ピンクは相手で危険を煽るような色、グリーンは自分でポジティブ色、といったイメージですね。
そういったセオリーはどこかで学んだ?
高場:特にないですね。作りながら作っていきました。ただ一般的な話ですね。例えば赤だったらアラート、グリーンは信号の色だったり。世の中にあるようなカラーリングだったり。アイコンだけで表現できることにもこだわりました。facebookって下に補助のテキストが入ってるんですが、こういうのはいらないなって思って。できるだけ文字を使わないのもこだわりましたね。

話を聞いているとなるほどと思う一方、突拍子もないアイデアというよりは基本に忠実だなという印象ですね。であれば尚更、これだけたくさんのアプリ開発者がいるなかで、どうして高場さんたちだけがここまで勢いよく成長したのか気になります。
高場:私のなかで2つ、他とは違うことがあるのかなと思っていることがあります。ひとつは海外のサービスを作った経験がある開発者が集まっていること、それともうひとつは失敗をした経験ですね。
ほう
高場:海外サービスって頭でこうだって分かっていたとしても、実際にはできないことが多いんです。例えば、世界の市場を眺めると、フラットデザインって本当に多いのですが、いざ、日本のゲームを見るとやはりキャラクターものが多くなってくる。
高場さんはアメーバピグの海外版などの開発に携わったんでしたよね。ピコがあまりうまくいかなかった経験とはどういうものだったんですか?
高場:アメーバピコはピグの成功を元に海外展開を狙ったものだったのですが、やはり日本人だけが対象のコミュニケーションサービスと違い、海外では人がどうしても分散してしまいます。具体的にはアメリカ人とインドネシア人がピコでコミュニケーションしても、なかなか言葉の問題で成立しにくい。
確かに言葉の壁がありますね。
高場:一方で、手を振ったりとかアバターを着飾ったりするコミュニケーションは上手くいったんです。

なるほど。そういう上手くいった経験を今回のBrainWarsに活かした。
高場:日本のサービスをローカライズするだけではやはり上手くいかない。それは学びましたね。
海外には拠点作ったり、例えば米国法人を設立したり、という「文化の中に入っていく」というようなことは必要ないですか?
高場:アングリーバードのRovioなどの例もありますが、開発は自国で様々な国の方を雇用してサポート体制を作り、各国にはマーケティングの拠点を置く、というのが理想ですね。彼らに出来て、日本で出来ないことはないと思っています。
ーーこの指摘は重要な内容を含んでいると思う。私は過去、いわゆる「デラウェア登記」のスタートアップをいくつも見てきたが、正直、なぜリスクだらけのスタートアップがわざわざ更なるリスクを求めて海外登記するのか疑問に思っていた。
実際、Whillのように「マーケットが北米にしかない」から北米で法人を作る、という明確な理由があれば別だが、結果的に日本でできるのであればここから攻めた方がいい。トランスリミットはそういう意味で「日本から海外」を実現した好例とも言える。話を続けよう。
色々な支援者がいると思いますが、役に立ったアドバイスを教えてもらえますか?
高場:そうですねCocoPPaの手嶋さん(ユナイテッド取締役の手嶋浩己氏)はやはり私と同じ経験をされているので、例えば「パッ」と世界に広まった瞬間はプッシュ通知の時間を各国の時間に合わせた方がいいよ、とか細かい助言をいただきました。
細かい(笑
高場:でも、そういう国の問題ってあって、中国の方からすると台湾と香港を別の国とすることに違和感を感じるんですね。逆に台湾や香港の方からは一緒にされると困るという。それで国と地域、という形で分けるようにしたりしました。こういう問題ってすぐに対応しなければならないので、アプリ申請の処理を待たないで対応できるよう、別のファイルにしたり、そういう工夫もしてます。
細かい部分で海外対応はやはりノウハウ持ってる方に教えてもらう必要があるということですね。
直近の事業拡大はゲームを柱に、中長期では未来を語れる体制を作る
では、ちょっと話を変えて、今後の事業について。やはり冒頭でお話しした通り、ゲームという事業はどうしてもアップダウンが激しい側面があります。今後、BrainWarsはどういう方向で事業拡大を狙うのでしょうか。
高場:事業モデルとしてやはり直近はこのゲーム、という形式はしばらく続くかなと思っています。ただ、今後、タイトルを増やすにしても競合マッピングを見て空いてる場所を攻めるというよりは、一発必中というか、しっかりしたものを作るという方向にフォーカスしようと考えてます。
BrainWarsには次期バージョンの話もありましたね。
高場:実は、現在大きめのアップデートを準備中で、今後、BrainWarsを頭を使うプラットフォームのようなものにしようと考えているんです。ユーザー同士のコミュニティも盛り上がっていて、eスポーツ(※米国で盛んな賞金も出るトーナメント形式のゲーム大会)のような雰囲気もあるんです。そちらの方向も興味ありますね。
ちなみにビジネスモデルは?
高場:広告と課金ですね。現在は半分半分ぐらいの割合です。

直近はもちろん、この体制を作る、ということにフォーカスすれば正しい選択に思えます。では、その後、中長期の視点ではどのように考えてます?まだゲームを作り続ける?
高場:ご存知の通り、やはりゲームというのは売り上げの波が激しいのが事実です。でも、この世界で戦えるタイトルを開発するチームをしっかりと作れば、今後、この体制でゲーム以外にも事業を拡大することは可能だと考えてます。
ーー確かに、これは逆の話だがミクシィはソーシャルプラットフォームの開発からあのビッグヒットを生み出すことに成功した。ゲーム開発で体制を作り、それを基盤に事業拡大を狙う、というアイデアに抵抗感はあまりない。もちろんそれができるかどうかは別の次元の話だが。
現在って何人の体制でした?
高場:役職員、アルバイトも合わせて10人ほどになりました。先日、新卒の方も内定出したんですよ。
新卒もう取ったんですね。早い(笑。では最後の質問ですが、先日資本業務提携されたLINEとはどういった連携をするなど決まったことがあれば。
高場:年明けぐらいからタイトルを提供しますが、まだそれ以上のことはこれからですね。
なるほど。ありがとうございました。
ーーさて、いかがだっただろうか。
トランスリミットがここまで自然増で一気にダウンロード数を増やした要因は、やはり選んだテーマに教育という背景があったこと、それに加えて高場氏らの海外向けサービス開発の経験や失敗が生きているように感じた。
ひとつひとつの条件はありそうでも掛け合わせるとなかなかなかったりするものなのだ。何よりも数字はそれを証明している。
課題はもちろんまだまだ多く、やるべきことも多そうだが、折角ここまで一気に成長したのだ。行けるところまでいって欲しいと思うのが外野の素直な気持ちかもしれない。
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待