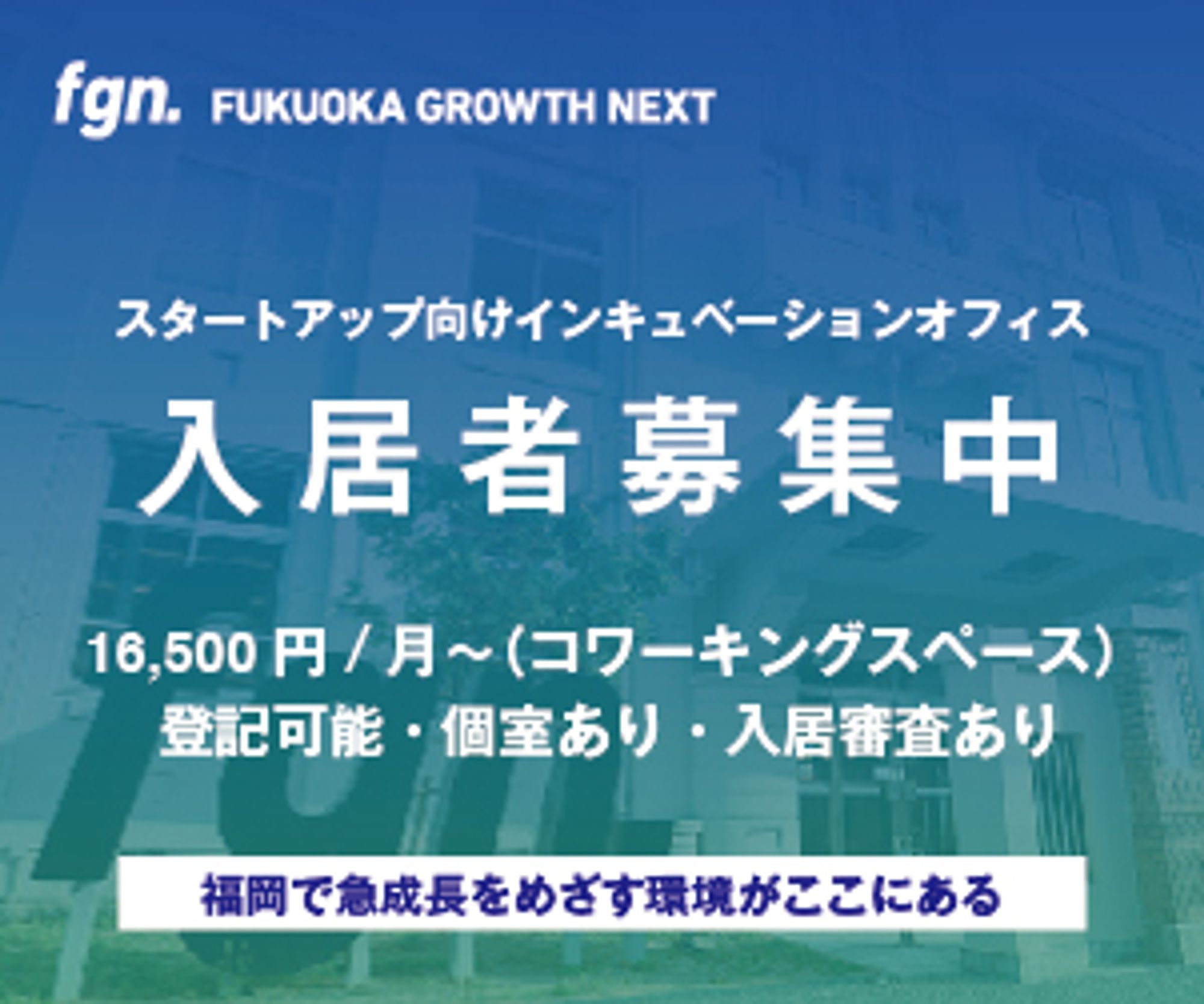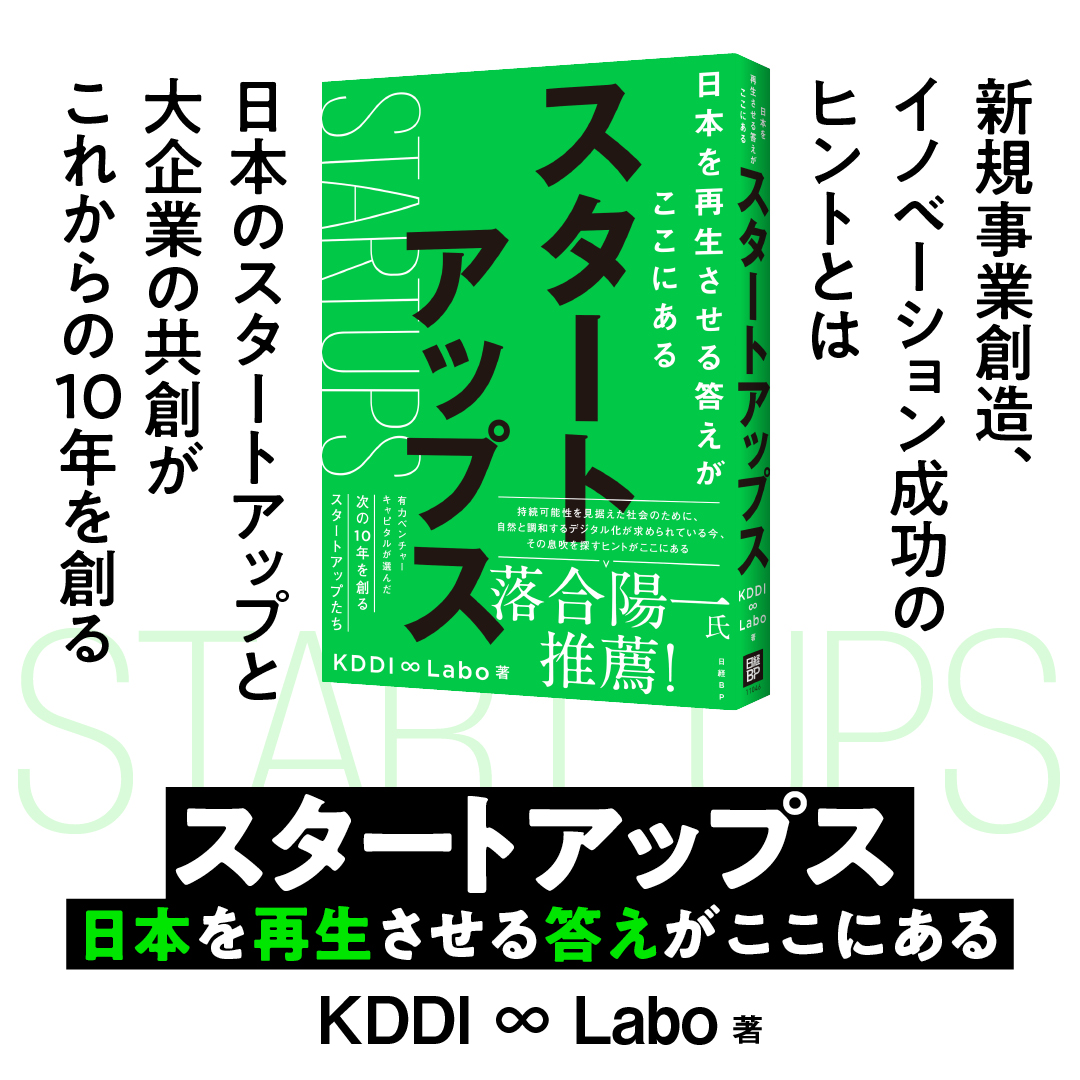<ピックアップ>Article: Young Users Zoom In on Instagram
米調査コンサルティングのFrank N. Magid Associatesが2012年から2014年までの米国でのソーシャルネットワークサービスの利用状況をまとめております。(13歳から64歳を対象)
2014年12月末時点の数字として、ソーシャルネットワークサービスで何を使っているか、という質問に対してfacebookが90%と高く、Twitterの39%、Google+の37%が同等で続きますが、その次にはInstagramの32%がやってきているのが興味深いところです。その後はPinterest(30%)、LinkedIn(29%)、SnapChat(18%)となっております。
こういう場合にはYouTubeが必ず上位に現れるのですが、入ってないのはG+に含まれているのかそれとも対象から外れているか、どちらかでしょう。ともあれ年を追うごとにテキスト主体のコミュニケーションからビジュアルコミュニケーションに移りつつあることがよく分かる数字です。
eMarketerではFrank N. Magid Associatesのもう一つの数字を掲載しているのですが、これも面白い傾向がみられます。2014年末時点での年代別ソーシャルネットワークの利用状況で、やはり予想通りというか、10代から20代はSnapChatの強さが目立ちますね。Instagram、Tumblr、Tinderもややその傾向で、逆に年代が上がると目立って強いサービスはなく、平均的にサービスを利用しているのがわかります。(Tinderの利用率が40代半ばを越えると一気に下落している様子が味わい深くて気になりました)
via eMarketer Articles and Newsroom Posts
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待