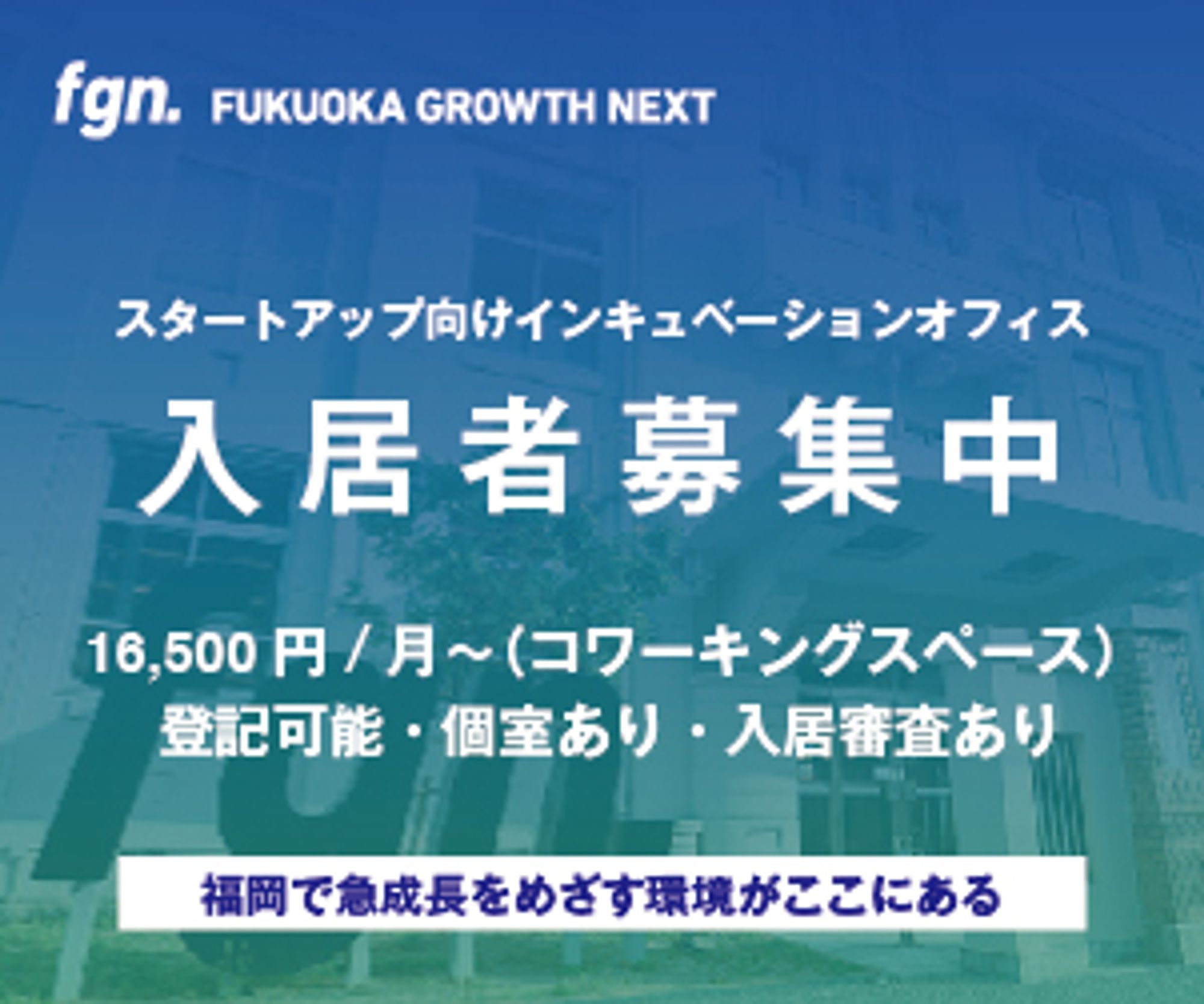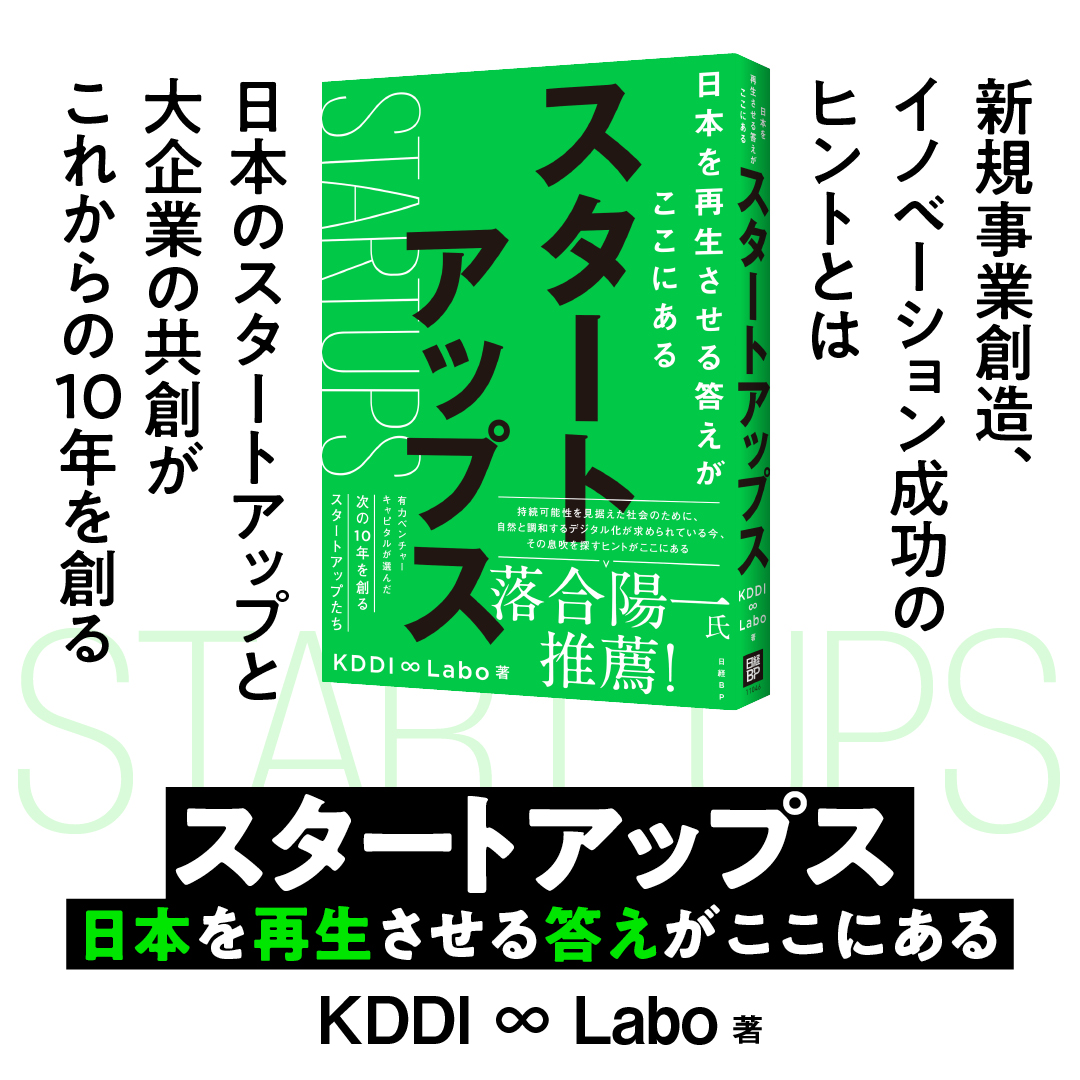<ピックアップ> Will Pokémon Go help AR surpass VR in consumer adoption?
ポケモンGO祭り、日本でもわかりやすいぐらいにヒットしていますね。海外でそうであったように、交通事故や崖から落ちる、警察署でポケモン探して捕まる、この手のネタは時間の問題でしょう。人類の再現性に期待しています。
そういう話題はさておき、個人的に大変気になっているのがこのゲームが与えるVR(バーチャルリアリティ)・AR(拡張現実)への影響です。ご存知の方も多いと思いますがこの市場はまだ初期段階であり、さらに言うとVRが立ち上がってその後にARがやってくるだろう(その先にはMR・複合現実がある)と言われています。
しかし、ポケモンGOはこの順番を変えるどころか、一気にマス・マーケットまで拡張してちびっ子たちを(お金払う親も一緒に)マクドナルドまで連れていくという、10年後ぐらいにようやくできるだろうなと思っていたシーンを実現してしまいました。
この件についてRecodeに転載されていた考察が私の今の心境を綺麗に整理してくれていたのでそちらを引用しながらこの市場に与える影響を考えてみたいと思います。
元はTech.pinionというオピニオン投稿サイトに公開されていた記事で、書いたのはTim Bajarin氏。Creative Strategiesのコンサルタントとして大手クライアントを担当してきた人物です。で、彼の主張をまとめるとこんな感じ。
- ポケモンGOはARをうまく活用した例であり、「Next Big Things」であるバーチャルリアリティを追い越したのではと考える人もいる一方で、単なる一時期の現象と捉えてる人もいる。
- VRがコンシューマーレベルに広がるには少なくとも2020年まで待たなくてはならない。この予想は自分の長年の経験から割り出したものである。
- 新たなテクノロジーは三つのステージで広がりを見せる。それはすなわち次のようなものだ。
- ファーストステージ:VRの場合はハイエンドゲームが牽引した。マーケットにおけるバリュープロポジションでVRがどのように働くのかを確定させるタイミング’。競合たちが出現し、価格は20%から25%落ちる。
- セカンドステージ:各業界で利用が進み、VRでは旅行や不動産、エンタメなどでサービス提供が始まる。業界と利用者の教育が促進され、2年から4年でこのステージが終わる。価格は15%から35%下がる。
- サードステージ:アーリーアダプターやバーティカルからの卒業で、幅広く消費者に向けてサービスが提供されるタイミング。価格は初期段階に比べて60%から70%落ちる。
Bajarin氏の主張ではARはこのファーストステージにあり、あと1年から2年でバーティカルに移行する「はず」だったんですね。マスマーケットに移行するには少なくともあと10年から15年という計算です。VRについてはもうちょっと早く、2020年にはマスマーケットで人々が手に取りやすい価格帯で、しっかりと価値も提供できるものができていると。
ちなみに現時点でのARというのはMicrosoftのHoloLensが代表例であり、ちょっと前にあったGoogle Glassや国内でも話題になったセカイカメラ、テレパシーといったアプリやアイウェアはそういう意味では早すぎたと言えるかもしれません。
こういう状況の中でのポケモンGOの登場は大変な衝撃だったわけです。
一方でこのようにポケモンGOをARにカテゴライズするのは間違いだという論もあります。個人的にはそこまで細かく定義しなくてもARの普及に一役買ってる以上、いいんじゃないかと思ったりもしたのですが、こういうパラダイムのシフトを考えると、手放しにポケモンGOを「ARゲームだ」と撒き散らかすのは少なくともメディアとしては間違ってるかもしれません。
Bajarin氏はこれらの整理の上で、ポケモンGOが市場に対してARがどのような効果をもたらすかという「価値」を提示してくれたことを評価しつつ、やはりこの3つのステージはその通りにやってくるとし、ARがVRを抜き去ってトレンド化することはないと予想しています。
VRとARは並べて語られることが多いので混同しがちですが、没入感やデバイスなど全く違います。ただ個人的な予想はBajarin氏と少し違っていて、VRとARはほぼ同じ速度でこの3つのステージを駆け抜けるのではと考えてます。
セカイカメラを取材していた時(リンク先は当時の私の取材記事)、私の大きな疑念はこの技術が何を目的とするのだろうか、というものでした。それはARというよりは位置情報サービスとしての視点です。(ARは位置情報と一心同体です)
※YouTube・当時からこういうARのコンセプトはあり、セカイカメラもこの世界観を目指していた
結果、Foursquareを始めとする位置関連の先行サービスはO2Oという言葉に傾倒し、セカイカメラも最終形態としてTabというおでかけ情報のサービスに変化しています。
つまり数年前のARは面白いインターフェースの一つであり、サービスのコアとは少しズレていたのです。ARは電池も食いますし、位置情報がズレるとほとんど意味のないものになる、というのが当時の状況でした。
ポケモンGOはそういう意味で、初めてARの役割、楽しさ、創造性を分かりやすく一般に証明してくれたと言えるでしょう。漫画やアニメで読んだ、ゲームで遊んだ記憶がそのまま実現するわけですから興奮する人たちが多いのも頷けるのです。
人を動かすのは情報や操作ではなく感動体験であり、それを実現したポケモンGO・ARビューの役割は大きかったと。もちろんIPの力も大きいですが。
この印象はVRが証明した没入感の感動と同様のものかもしれません。Bajarin氏が言うところのファーストステージにおける「価値の証明」です。
今後、ARはHoloLensをはじめとする高度なオーバーレイ・操作インターフェース技術により単なる重ね絵を超える感動体験を提供してくれることになるでしょう。それにはBajarin氏の言う通り、数年を待たなければなりません。しかし、市場に理解があるという状況はそれを幾分か早めてくれる予感がします。

ポケモンGOに習ったゲームの登場や「ポケモングラス」と言われるVufineのようなAR用途のグラス機器などは分かりやすい牽引例として注目しています。
Image Credit : VentureBeat
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待