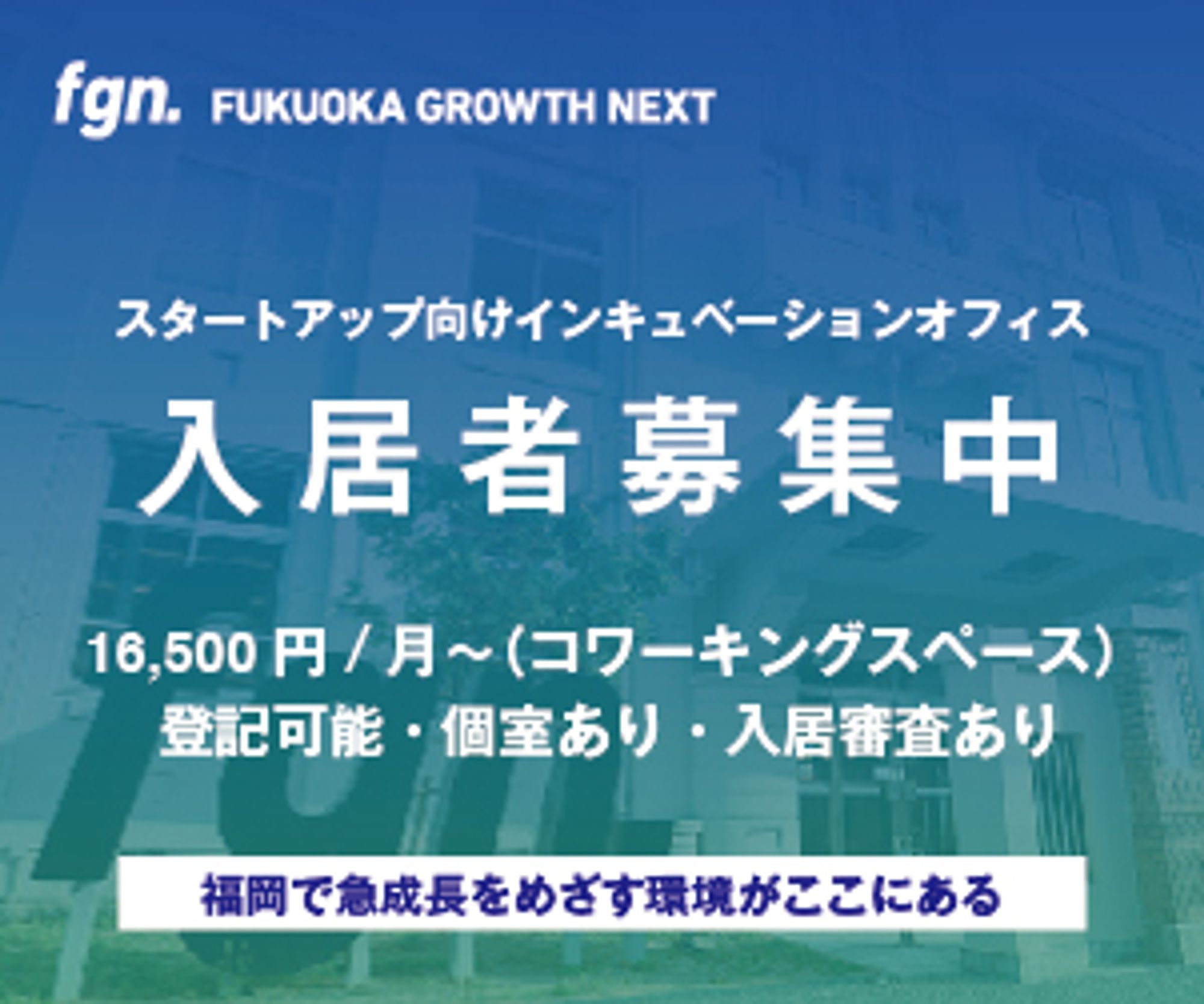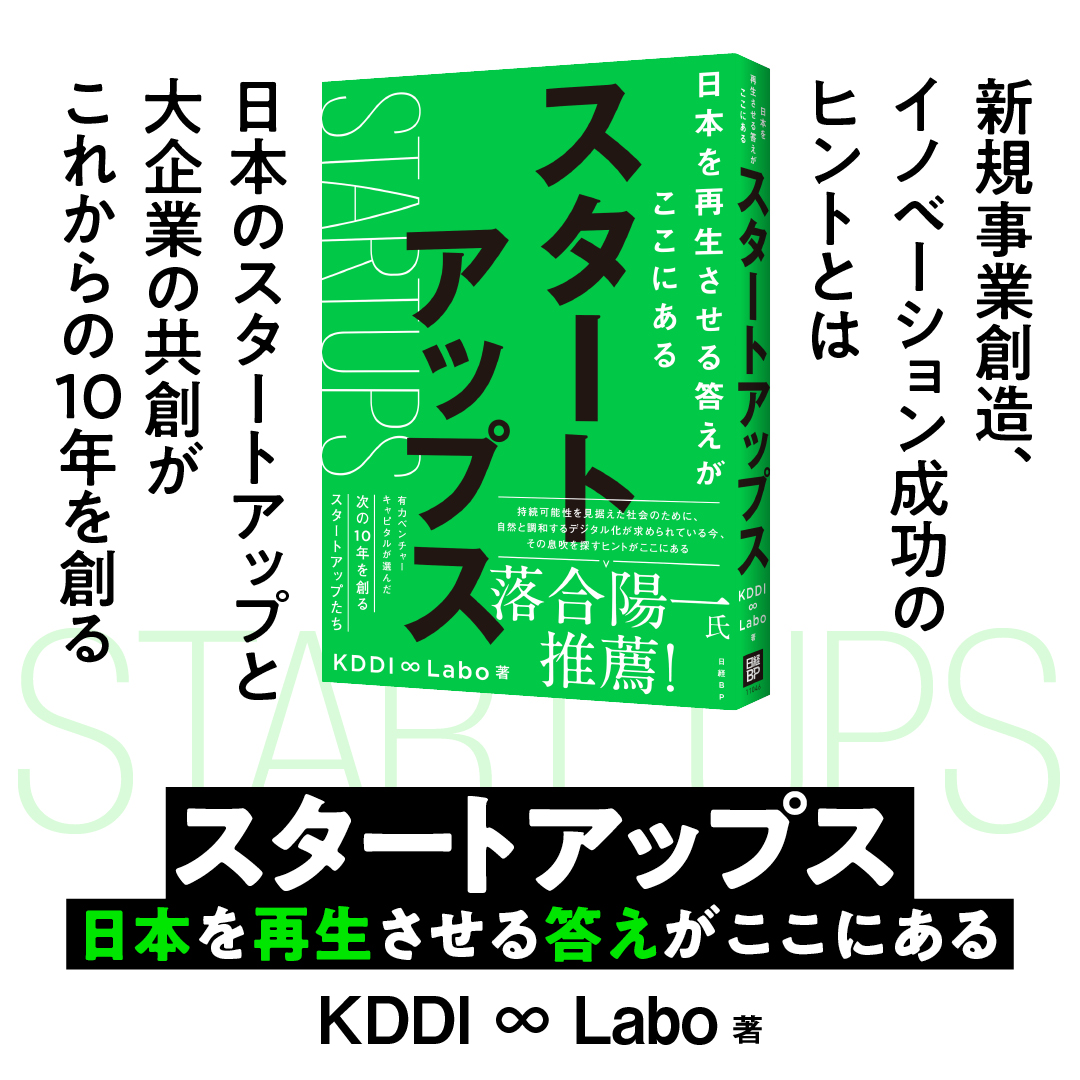Facebookが偽ニュース(フェイク・ニュース)の問題に取り組むと宣言したのが昨年11月。その後、具体的なプランとして5つの項目を挙げて対策すると公表していました。
この内のトップバッター、「ユーザーが不正確と判断したストーリーに警告ラベルを追加」が静かにスタートしているようです。発見したのがGizmodoで、偽情報と思われるサイトの記事の下に表示されることになるそうです。(下のツイート参照)
Facebook is flagging links to fake sites now, looks like: pic.twitter.com/N7xaWDkdYA
— Anna Merlan (@annamerlan) March 3, 2017
個人的にFortuneの解説が分かりよかったのでそちらを読むと、嘘かどうかの判断はPolitifactやSnopes.comなどの独立した調査機関によってチェックされるとしています。
これらの組織は「事実チェックの原則」へ署名したジャーナリズムの非営利団体であるPoynter Instituteによって運営されている。この原則には資金と情報源において中立性および透明性が盛り込まれている。(Fortune記事より引用)
Business Insiderの記述ではもう少し詳しく解説しています。
Facebookはジャーナリズム非営利団体Poynterが運営する国際的で超党派的なファクトチェッキングネットワークに参加する多数のメディアと提携した。リストには42の組織が含まれているが、FacebookはまずSnopes、Factcheck.org、ABC News、PolitiFactの4つを採用している。(すべてのファクトチェッカーは、Poynterが作成した原則規定を遵守する必要がある)。(Business Insiderより引用)
ただ、やっぱり第三者機関によるチェックといってもチェックするまでの時間(Recodeの報道では数日)が必要で、誰かが嘘じゃね?と通報してから第三者機関でチェック、「みんな!これは嘘の情報です!拡散しないで!」と警告するまでのタイムラグだけで十分に延焼する可能性があります。
日本ではまだ(少なくとも私が見たところですが関連情報もないので)始まっていないこの通報システムですが、それ以前の偽情報かどうかを判断する第三者機関としては、今年春に偽ニュース対策に取り組む協議会が設立されると朝日新聞が報じています。
システム同様に難しいのは判断の基準で、明らかなクリック詐欺みたいなサイトは別として、匿名のリークサイトみたいなとこに流れる真偽不明の情報や、思いっきり右・左に寄った、片方からは嘘としか思えないトンデモ情報の扱い、個人的にもこのネットらしいと言えばネットっぽい話題を、特定団体やプラットフォームがどう判断するのかというのは興味深いところであります。
via Gizmodo、Fortune、Recode、Business Insider
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待