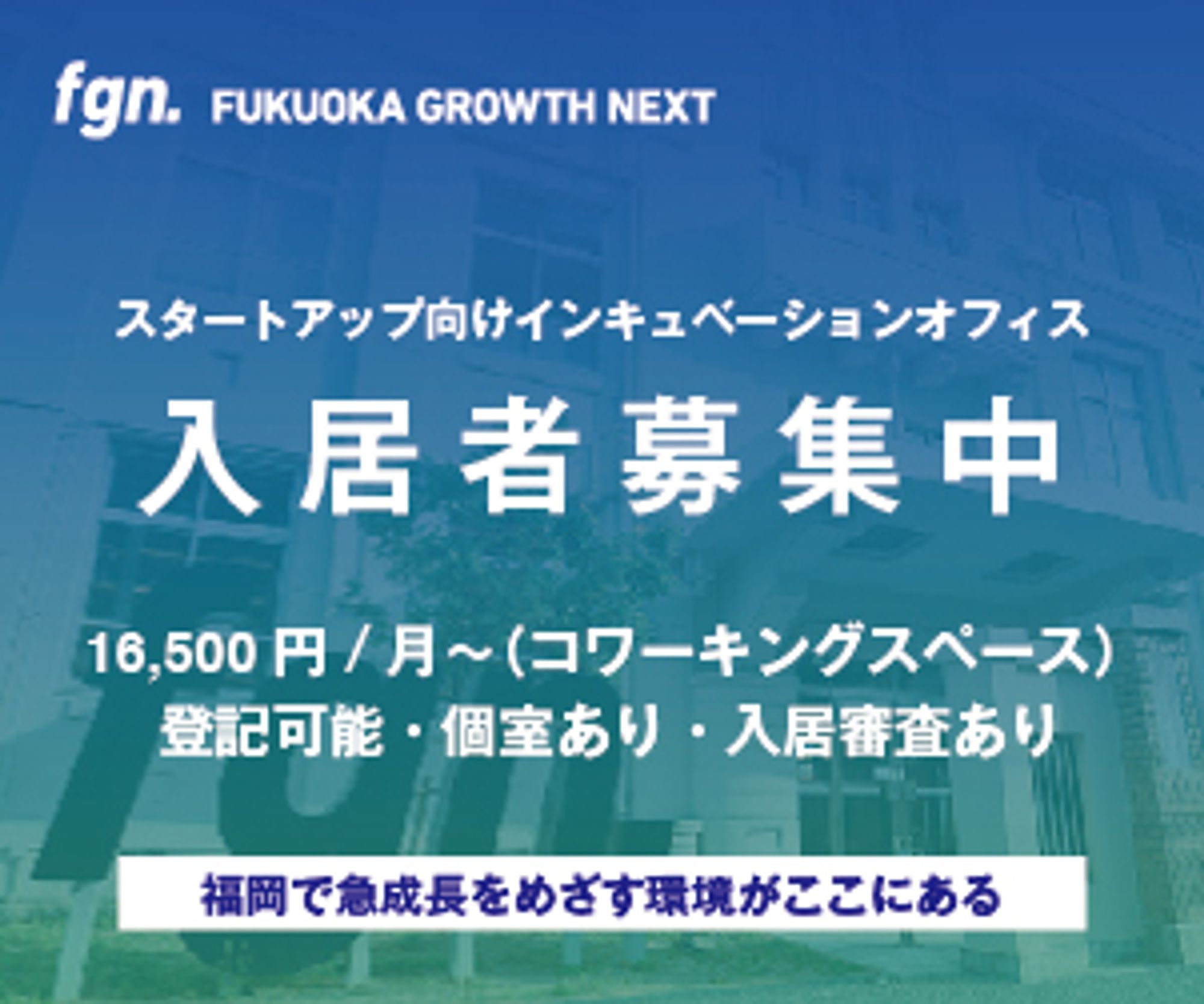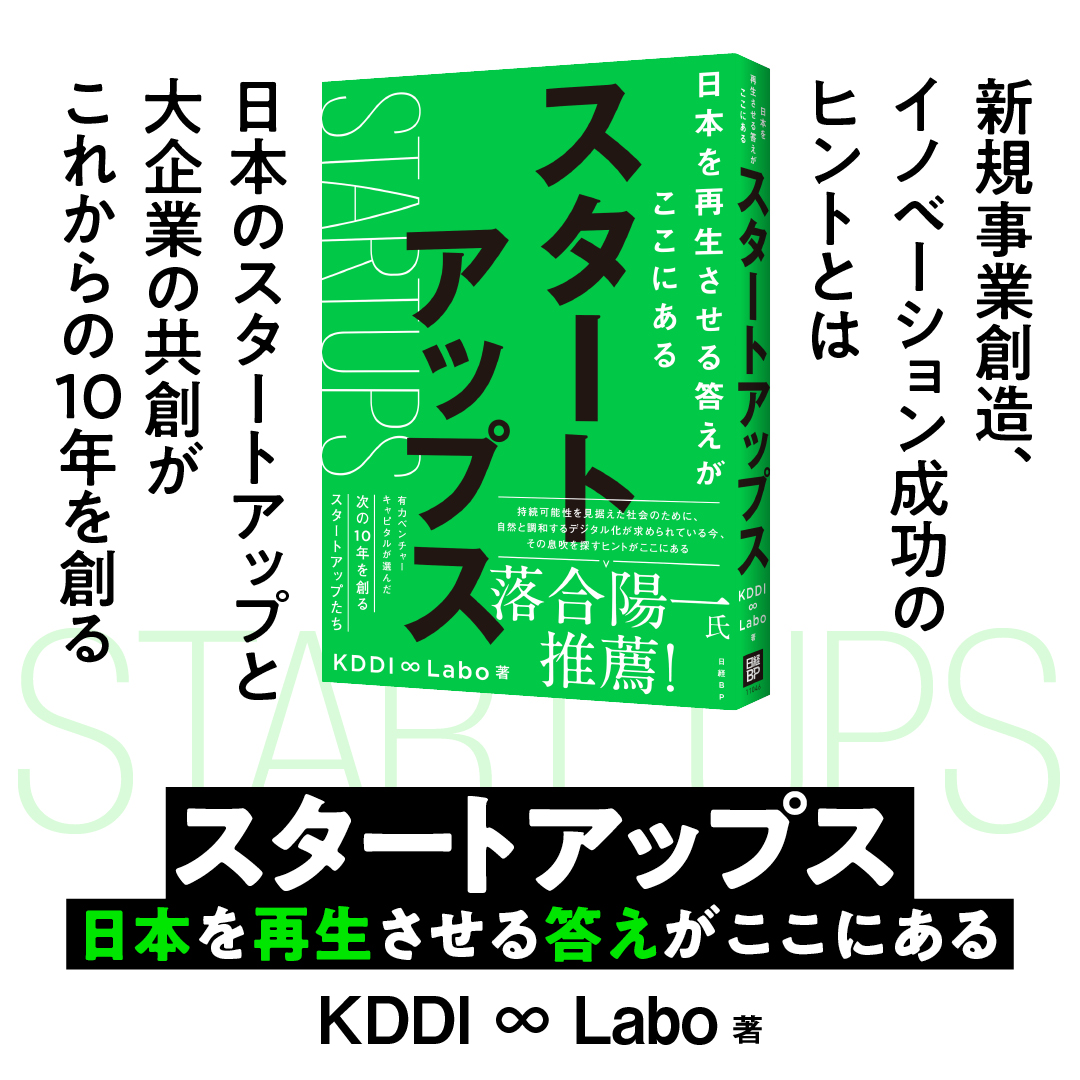イラストコミュニケーションサービス「pixiv」を運営するピクシブは26日、クリエイターの創作活動を継続的に支援できるサービス「pixivFANBOX(ピクシブファンボックス)」を、全クリエイター向けにローンチした。pixivFANBOX では、クリエイターがファンから月額制で支援を受けることで、自由に創作活動を続け新しいコンテンツ創出に挑戦することができ、一方で、ファンはクリエイターとより密なコミュニケーションを楽しむことができる。
pixivFANBOX は一部クリエイターを対象に2016年12月にローンチし、機能拡充を進めながら段階的にクリエイターに FANBOX 開設の機能を開放してきた。pixivFANBOX 上で、クリエイターは、イラスト・小説・漫画・動画・音楽などのコンテンツを掲載可能。以前は、クリエイターがコンテンツを掲載できなかった月はファンからの支援金を受け取れなかったり、過去のバックナンバーのコンテンツを読むには別途購入したりする必要があったが、今月1日のリニューアルで完全サブスクリプション型に移行していた。
今回の pixivFANBOX の全クリエイター向けローンチを受けて、通常は、ファンからの月額支援金総額から決済手数料5%を差し引いた金額がクリエイターに支払われるのに対し、4月26日〜5月31日まで支払金総額にピクシブが20%を上乗せして支払うキャンペーンを実施する。5月31日までに pixivFANBOX にアカウントを登録し、キャンペーン期間中に一度でもファンが10名に達したクリエイターが対象となる。
via pixiv
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待