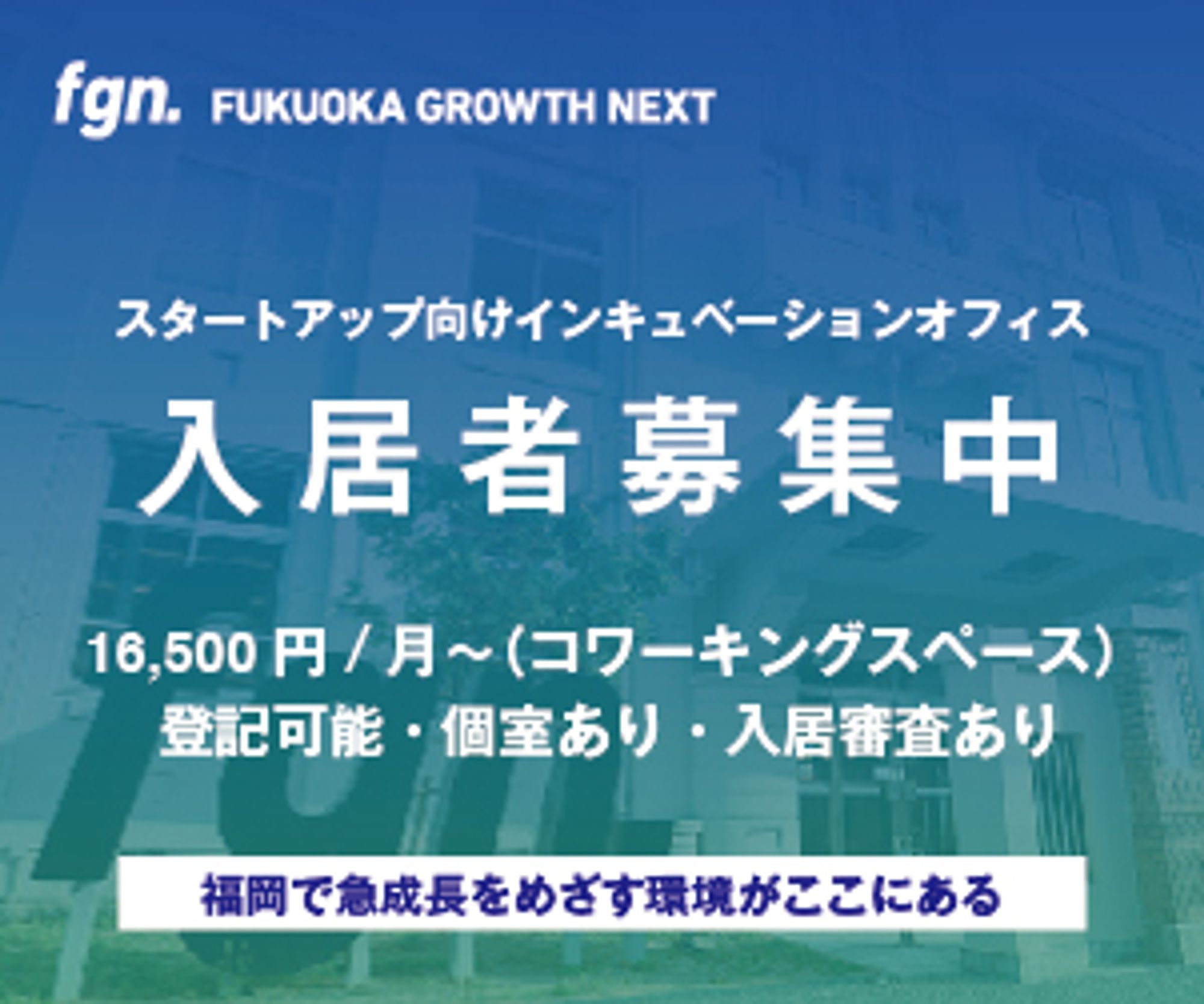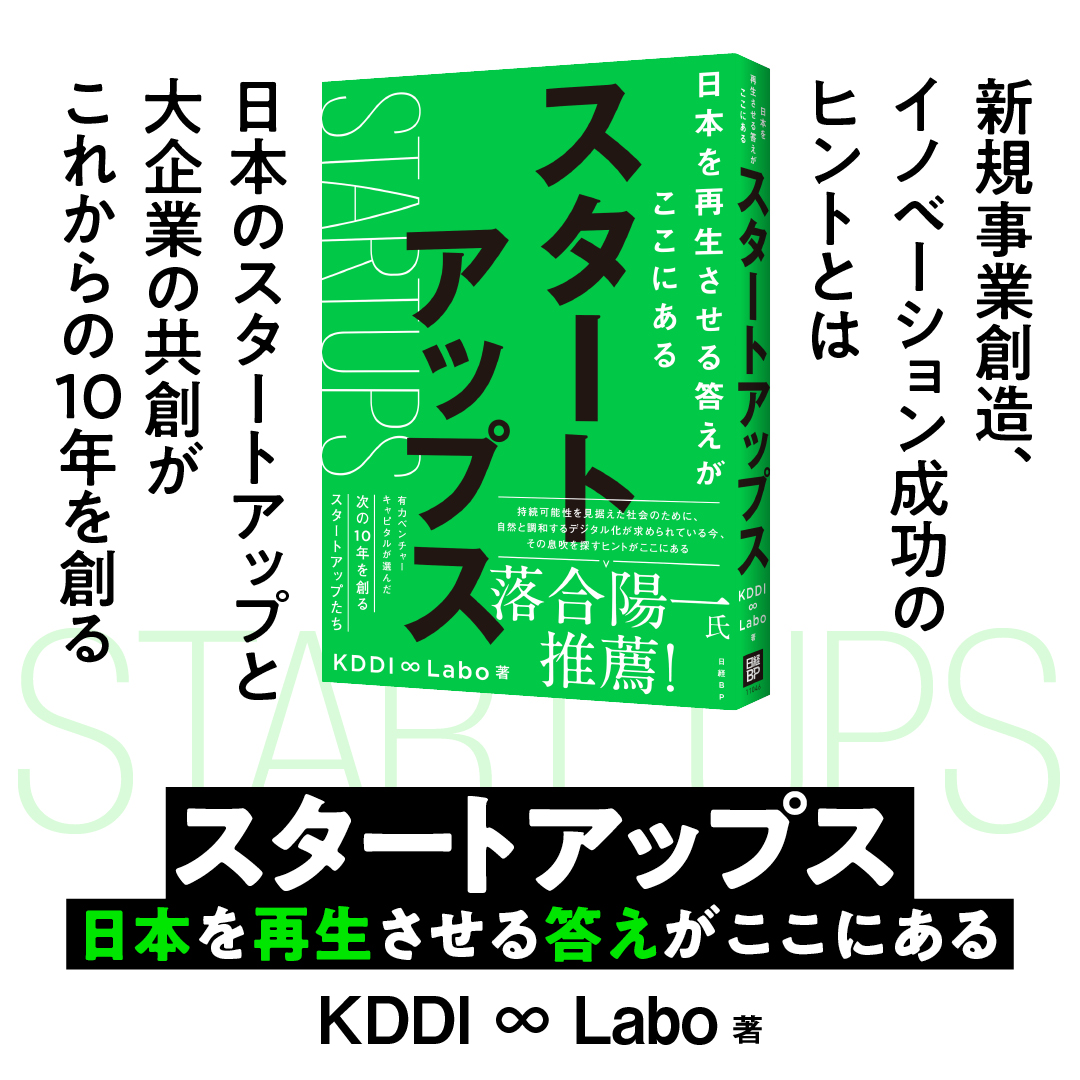ロボティクススタートアップ の GITAI に元 SCHAFT の中西雄飛氏がジョインしたのをお伝えしてから2週間、その後、同社には宇宙関連事業者との提携話が相次いでいるようだ。

Image credit: Gitai
先週には、衛星通信大手のスカパー JSAT(東証:9412)との業務提携検討に関する覚書締結が発表された。スカパー JSAT は17機の通信衛星を保有するアジア最大の衛星オペレータだ。この業務提携検討の中で、具体的に何が進められるかは明らかにされていないが、GITAI が提供可能な機能と、衛星運用業界が直面する課題を見ていくと、いくつかの仮説が考えられる。
一つは、衛星の軌道投入の方法として一般的な地上からのロケットによる直打ち上げだけでなく、国際宇宙ステーションなどからの衛星放出を行う方法。打上げ環境条件が厳しくない、打上げ機会が多いなどのメリットがある。GITAI の遠隔制御ロボットと組み合わせれば、こういった衛星の放出前チェックアウト作業や放出作業も、宇宙飛行士を介在させずに行える可能性がある。
一方、人工衛星の寿命は概ね、軌道修正のために必要な薬剤の搭載可能量と、太陽電池やバッテリーの寿命に依存するところが大きいとされる。地球の重力圏にある静止衛星は高度が低下すると静止状態を維持できなくなるため、これを補正するために定期的に軌道修正を行う必要があるが、そのための薬剤の搭載可能量には上限がある。太陽電池は宇宙放射線の影響を受けやすく、バッテリーは充放電を繰り返しているため、いずれも数年程度で寿命を迎えてしまう。
寿命を終えた衛星を捕獲し、宇宙で薬剤の再充填や部品の交換、宇宙空間への再放出が一般化されれば、衛星の寿命は圧倒的に伸ばせるようになる。これまで寿命を終えた衛星は、軌道制御して意図的に大気圏突入させ焼却処分するのが一般的だったが、ロボットを使った衛星の延命措置が実用的になれば、衛星運用の初期コストや運営コストも圧倒的に改善されるようになるだろう。

Image credit: Gitai
また、GITAI は25日、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と共同研究契約の締結を発表した。
共同研究契約の締結に先立ち、GITAI は JAXA 筑波宇宙センターの国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟模擬フィールドで、ロボットによる宇宙飛行士の作業代替実験を実施したという。この実験では、スイッチ操作、工具操作、柔軟物操作、負荷の高い作業など汎用的な作業を1台のロボットで実施できる性能が求められる。
実験には複数のロボティクス企業が参加したが、GITAI のロボットはその中でも高いスコア(18の作業タスクのうち13に成功=72%)を獲得。今回の宇宙飛行士代替の適用可能性を評価するための共同研究契約締結に至った。この共同研究が目指すところは、先日の記事に書いた通りだ。JAXA は「きぼう」からの衛星放出事業も促進しており、スカパー JSAT との提携と相まって、宇宙関連ビジネスの効率性向上やコストダウンに寄与することが期待される。
<参考文献>
- Want to snag a satellite? Try a net(欧州宇宙機関)
- 宇宙政策委員会 宇宙産業振興小委員会 第2回会合 スカパーJSAT 提出資料 その2(内閣府)
- 小型衛星放出機構(JAXA)
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待