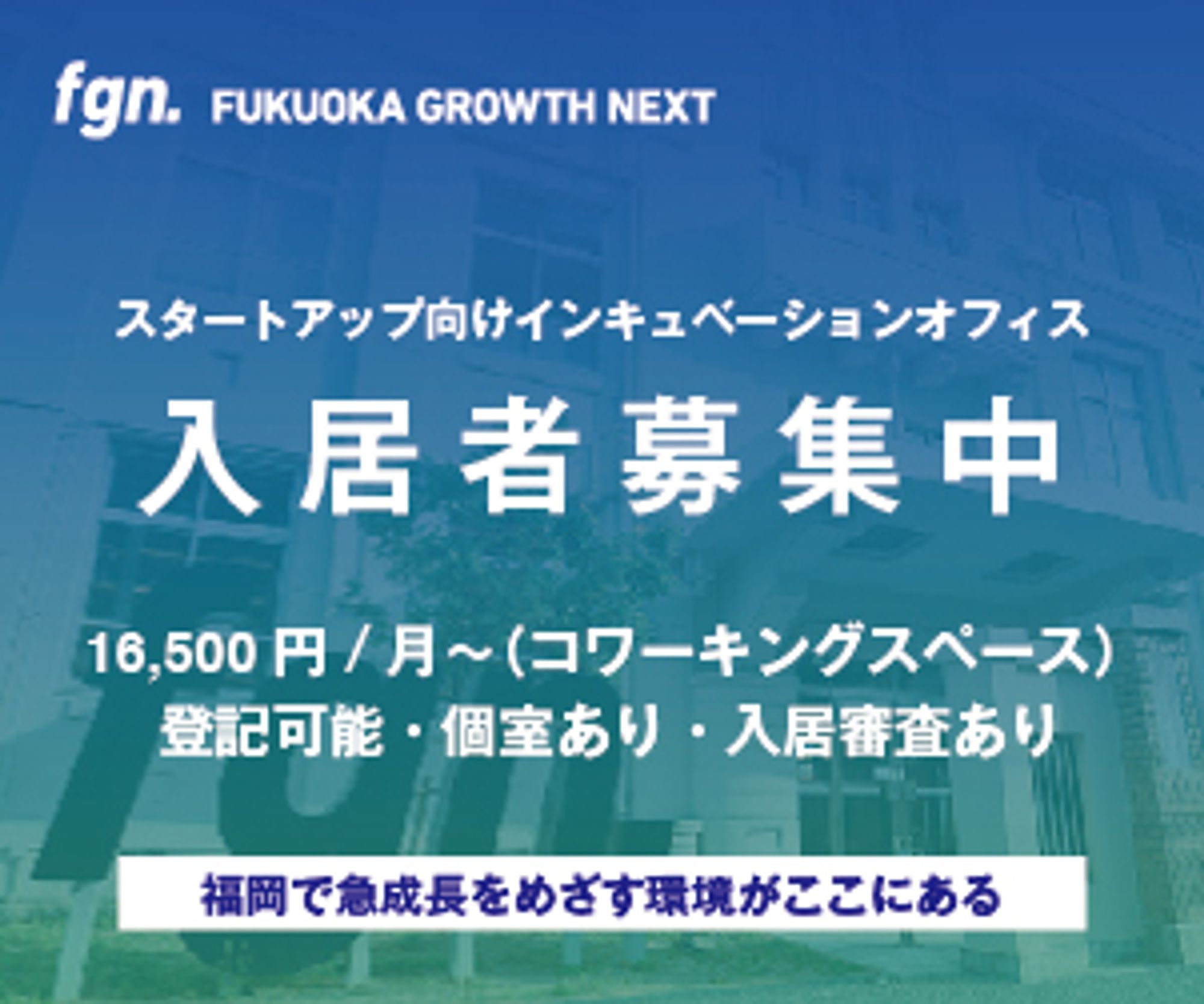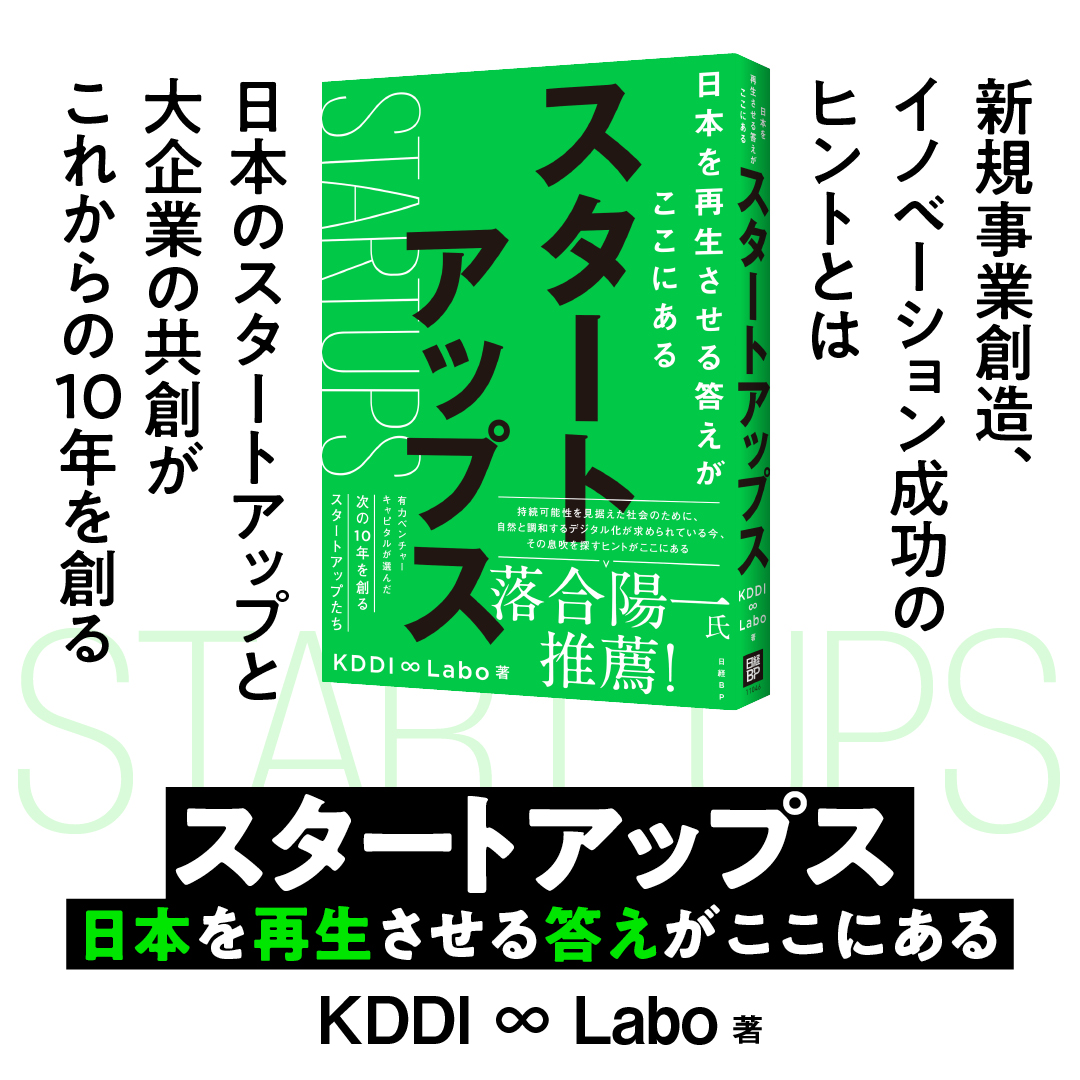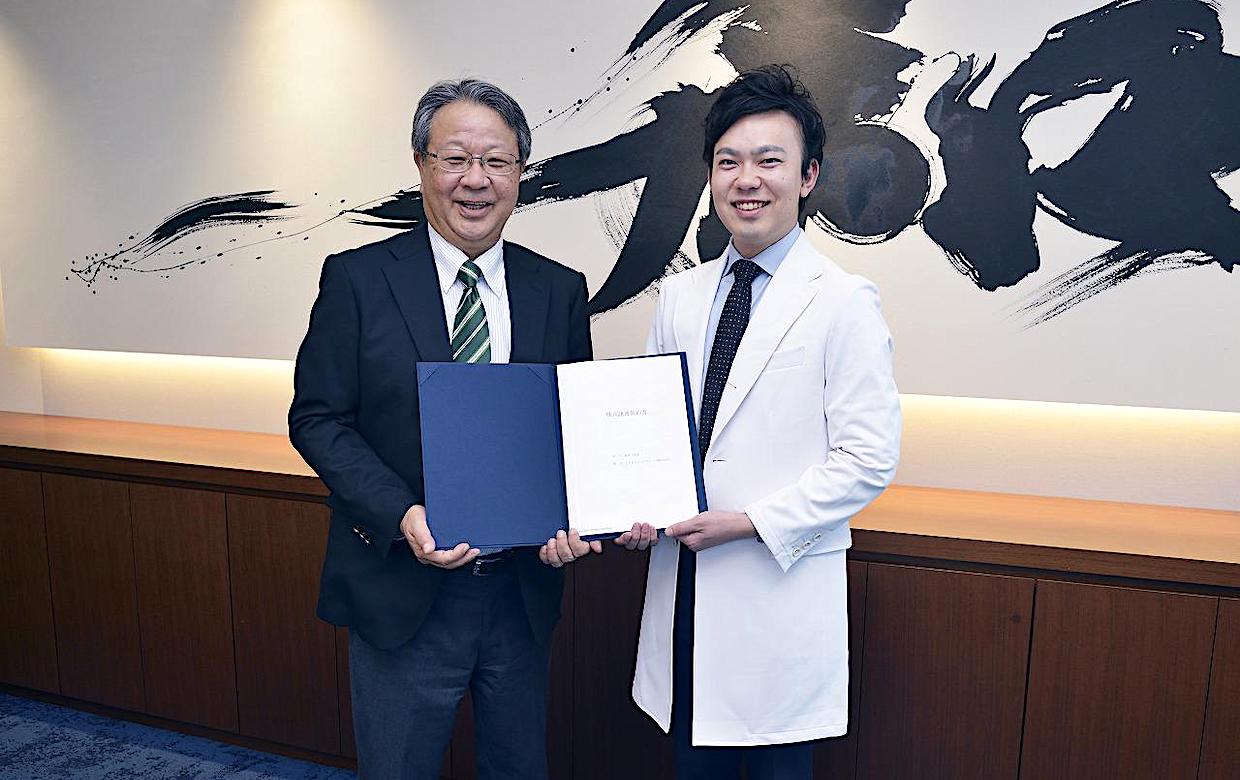本稿は世界のスタートアップシーンを伝える起業家コミュニティFreaks.iD編集部との連動記事。若手起業家向けの勉強会を定期的に開催中
20代起業家を対象に、彼らが考える新しいスタートアップのあり方を聞き出すインタビューシリーズ、前回登場のバーチャルYouTuber(VTuber)「にじさんじ」を運営するいちから代表取締役の田角陸さんに続いてはライブチケット見逃し防止「Freax(フリークス)」を運営するSpectra代表取締役の浅香直紀さんに登場いただきます。
今回もUpstart Ventures、上杉修平さんにインタビュワーとして参加してもらい、お話をうかがってきました(太字の質問は全て上杉氏。執筆・編集:平野武士)。

浅香直紀さん:1993年生まれ。中央大学卒。学生時代にTechouseでJEEKのマーケティング・新規事業開発を経てメルカリに入社。メルカリJPのグロースとソウゾウの立ち上げメンバーとしてメルカリ アッテの開発を担当。大学卒業後に新卒1期としてメルカリに入社し、メルカリ アッテのグロース・メルカリ メゾンズの立ち上げを経験。2018年3月にSpectraを創業し代表に就任
5月のiOSアプリ公開から4カ月、ジェネシア・ベンチャーズからの出資も公表されました
浅香:おかげさまでプロダクトに力を入れていくフェーズになったこともあり、絶賛採用中です(笑。特にクライアントエンジニアやマーケター、デザイナーを募集しています。またFreaxにとどまらず、音楽業界のデジタル化のサポートについては積極的に推進したいので、アーティストや事務所、レコード会社の方とはいろいろお話したいですね。
アーリーなステージの資金調達でどのあたりを意識されましたか
浅香:特にこのステージの株主はお金を出してくれるだけではなく、何かしらの価値を提供してくれる人がよかったと思っていました。C向けのプロダクトを作ることは決めていたので、株主としては、お世話になっていた人か、C向けのサービスの経験がある方。
中でもロジックでサービスを作って展開していくタイプの人、感性や直感でサービスを作るタイプの人の二種類の人を入れようと考えていました。
結構細かく考えられたんですね・・・。ところでSpectraでは当初、別の事業を並行していたそうですが
浅香:3つやっていたんですが、全てアイドル領域のウェブメディアでした。2018年4月、6月、8月に一個ずつ立ち上げており、トラフィックはそれぞれちゃんと出ていましたね。
なぜそれを捨てることに
浅香:SEOのメディアをやっていたのもあり人手も必要になって来て、共同創業者の露木(修斗氏・取締役)と次第にコミュニケーションが少なくなってきて、意思決定の軸がズレ始めたんです。それぞれが持ってる事業に対する意思決定で精一杯で、会社に対する意思決定ができなくなって。
11月にオフサイトして、今後どうするかを話し合おうという話になり、事業ドメインの再選定になりました。より大きい戦いをするために必要な意思決定は何か、というテーマです。

好調だったらなおさらズルズルいってしまいそうな状況ですね
浅香:SEOでフックするサービスだとライトなファンから広告でお金を取るビジネスモデルになってしまいます。一方で自分たちがやりたいのは、アイドル業界や音楽業界に良い影響を産むために、熱量の大きなファンの人を相手にしつつ、事業者側も幸せにするということだったんですよね。
お互いの考えが言語化できた
浅香:はい。音楽領域を選んだのはCDからストリーミングやライブといった収益構造の転換や、インディペンデントアーティストなど海外を中心としたアーティスト活動の形の変化などのタイミングが重なったことも大きいです。
昨今の情報の絶対量・収集チャネルの増加に対して課題感を感じていて、一貫して「情報を最適に届ける」ことで機会損失をなくすこと・機会を最大化することにフォーカスしよう、と決めました。
具体的にどういうフローで検討を進めたのでしょうか
浅香:サービス自体は情報のマッチングが適切でないことによる機会損失から検討しました。具体的には「自分たちのアーティスト時代に継続的な周知・集客が難しかったという原体験」「1ファンとしても情報を追いきれてない」という状況をベースに、過去の事業で「自分の好きなものの情報を受動的に網羅的に受け取る」というニーズを掛け合わせた感じです。
ライブチケットの見逃しを防ぐ、というピンポイントなテーマですが、どのような展開・拡大イメージがあるんでしょうか
浅香:足元では熱量の高いファンを中心に「ファン活動をするならFreax」といった純粋想起をとることですね。対応チケットサイトの増加や正しいイベント情報の表示といったデータ量・質の担保、ライブにいったログをストックで残せるようにする機能など、ファン活動を面で抑えられるようなサービスにしていく、というのが当面の予定です。
一方、中長期の視点では、Freaxが使われることで溜まる「事務所やレコード会社などの縛りがない横軸のファンの行動データ・嗜好性データ」を使って音楽業界のデータマーケティングのようなプレイヤーがデジタル化することで恩恵がある部分のサポートを計画しています。

ちょっと話題を変えてスタートアップする前の浅香さんについて。大学在学中はTechouseでインターンされてたそうで
浅香:大学2年生の夏休み、英語ならできると思って留学したんですが思ったようにコミュニケーションが取れず歯がゆい思いをしまして(笑。英語よりももっと汎用的な、ビジネススキルを身につけようと「インターン」で検索して一番上にヒットしたのがJEEKだったんです。
すごい。検索で人生が変わった(笑。その後、2016年の新卒一号社員でメルカリに
浅香:大学在学中にインターンでジョインしました。ソウゾウを立ち上げる前の松本(龍祐)さん直下で新規事業を作るという内容でした。その流れですね。
業務としてはどんな経験を
浅香:アッテの時は40人くらいの組織だったので、結構分業してやっていました。その後に携わったメゾンズは市場調査から入り、そのデータからどのジャンルのどの課題にフォーカスするのか、そのためにどんなサービスを作るべきかなど、基本的にサービスを作ることに関しては全部やっていました。
サービスをどう作るか、アジャイル開発、MVPの作り方などはメルカリで相当学ばせていただいたので、その経験は創業にかなり活きていると思います。
ソウゾウも新規事業がメインだった思いますが、社内の新規事業ではなく、自分で企業をスタートアップさせる時にどのようなギャップを感じましたか
浅香:メルカリで働いていた頃にいた自分の他のメンバーは、自分が採用したわけではなかったのですが、自社を創業した時は当然ですが自分で採用しなければなりません。ただメルカリの時のような強いメンバーを採用できるかと言われるとそれは相当難しい。一方でプロダクトは同じレベルのものを作りたいという葛藤はありました。
インターンの採用はかなりうまくできていて、採用媒体経由だと最高で週に100人以上の応募をいただけるぐらいにはなっています。ただ中途となるとまた話は別で、今いる組織を抜けて別の組織に入らなければいけないので、かなり難易度が高いですね。
逆にメルカリに残って新規事業を立ち上げる、という選択肢はなかったんですか
浅香:メルカリって何か新しいことをやる時、例えば青柳(直樹)さんを引っ張ってこれるような組織なんです。今後のキャリアを考えた時に、裁量権という観点で不安が残ったのは正直ありました。あと、メルカリにとってメリットがある形かどうかが肝であって、自分がどういうサービスをやりたいかとの折り合いをつけるのも難しかったですね。
で、自分たちで創業と
浅香:2017年の年末に会社を作る意思決定はしてたので、2018年頭からお世話になった人たちへの挨拶回りから開始しました。(イーストベンチャーズの松山)太河さんと松本さんには近況報告してすぐに出資するよとの言葉をいただいたり、その後、10Xの矢本(真丈)さんに堀井さん(Fablic創業者の堀井翔太氏)と大湯さん(コネヒト創業者の大湯俊介氏)をご紹介していただいたりして、2018年3月には会社設立、という流れです。

浅香さんを突き動かしてるものってなんですか
浅香:そもそも自身の成長意欲自体が強い方なんです。
良い意味でも悪い意味でも自分が好きな自分とか、自分が理想としている自分でありたいとか。昔から自分にできないものがあるのは好きじゃなくてなるべく多くのものをできるようになりたかったし、中長期でみて成長できないとか停滞しているとかは好きじゃないと思います。
なるほど。定性的で曖昧だけど大切な要素
浅香:自分の視野に入っているもので、良くできるものは少なからず良くしたいというのが、今のドメインを選んでいる理由の主要因だとも思います。
あとはバンドで曲をつくっていたこともあって、なにかを作っている行為自体もモチベーションになるかなと思っています。ものを作るのは苦しみも多いけどその分楽しいし、人が増えればよりクオリティやスピードも追求できるようになるというのは昔からもっている感覚です。
外的な要因でモチベートされることは
浅香:ユーザー数やKPIみたいな話ですよね。定量的な結果は嬉しいですが、より生々しさという意味ではやはり関係者からのフィードバックですね。それがあるから何かができるようになったとか、選択肢が増えるようになったとか。正の方向への差分が生まれるような体験が作れているかどうかを重要視していると思います。
事業の作り方について。事業のエグゼキューションで重要なポイントはどこにありますか
浅香:大きく二つあって、まず「合議しないこと」ですね。経営陣同士で意見が割れて絶対的な正解がない場合に、相手が責任を持ってやるといったことは信頼して任せる。
次に「本当に自分がやってレバレッジがかかるのか」。これはドメインに対する知識・経験や優先度・緊急度を鑑みて自分がやるべきかを常に考えることです。
専門家に意見を聞きに行くなり、副業として手伝ってもらうなり、採用するなり、会社が大きくなるための選択肢を常に持っておく必要があると感じます。
この二点に留意して、不可逆でなければ意思決定をし、そこにフルベットして結果をみることを意識しています。

すっきりした意思決定フレームワークですね。浅香さんにとって結果とは
浅香:結果というと、その明瞭さから定量的なものがよくあげられる気がするのですが、意外と自分たちが納得いくのって定性的とか曖昧な指標なんじゃないかなとは思っています。こういう立ち位置になったらとか、こういう価値が提供できるようになったらとか。
例えば音源CDからストリーミングに音源のタッチポイントが変化し、マーケットが転換点を迎える中で、アーティストも事務所もレコード会社も、多数の選択肢が考えられるようになったじゃないですか。
その中で、アーティスト・事務所・レコード会社など音楽業界の先達と一緒に、デジタルとリアルの境界線を溶かすのが音楽とITの間にいる僕らの役目だと思っています。結果、継続的に音楽を中心としたエンタメコンテンツが生まれてくる社会にしたいですよね。
インタビューも終盤ですが、実際にスタートアップしてみての感想をお聞きしたいです。いまってどのような方がメンターなんですか
浅香:株主については堀井さんや大湯さんには経営相談を定期的にさせていただいています。事業の細かいところというよりは、組織・採用や戦略レイヤーの相談が多いですね。起業家としての過去の経験と投資家としての視点をベースにフィードバックをもらっています。
サービスについては10X矢本さんです。メルカリ時代からサービス作りの相談をしていて、事業の仮説や戦術レイヤーなどの相談をさせていただいています。
他にはプロダクトづくりに関してはYCombinatorやポールグレアムの文献を参考にすることも多いです。また、ユーザーの巻き込み方やプロダクトの思想や広報は勝手にアル社を参考にさせてもらっています。
参考にしたいスタートアップが多くなりましたよね
浅香:同世代だとFOWDの久保田(涼矢)さんやBABELの杉山(大幹)さんは相談することが多いです。資金調達や資本政策の相談・情報共有から、組織づくりやプロダクトづくりのTipsレベルの共有まで色々です。
もちろん仕事以外の話もしています(笑。
起業のエコシステム全体で足りないなと思うことってありましたか
浅香:成功体験やメソッドは昔に比べて体系的にアウトプットされているように感じますが、失敗体験についてはまだ表に出てこないことが多いですよね。出しにくい部分も多そうですが、同じ轍を踏まないためにも狭い範囲でも良いので公開されるとエコシステムとか業界全体の底上げ的な意味では必要じゃないかなと。
あとは資本政策や採用は一回の重みが大きいということもあり、リファレンスについては投資家に対しても採用候補者に対してもフェアな形でもっととれるといいなとは思います。
長時間ありがとうございました!
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待