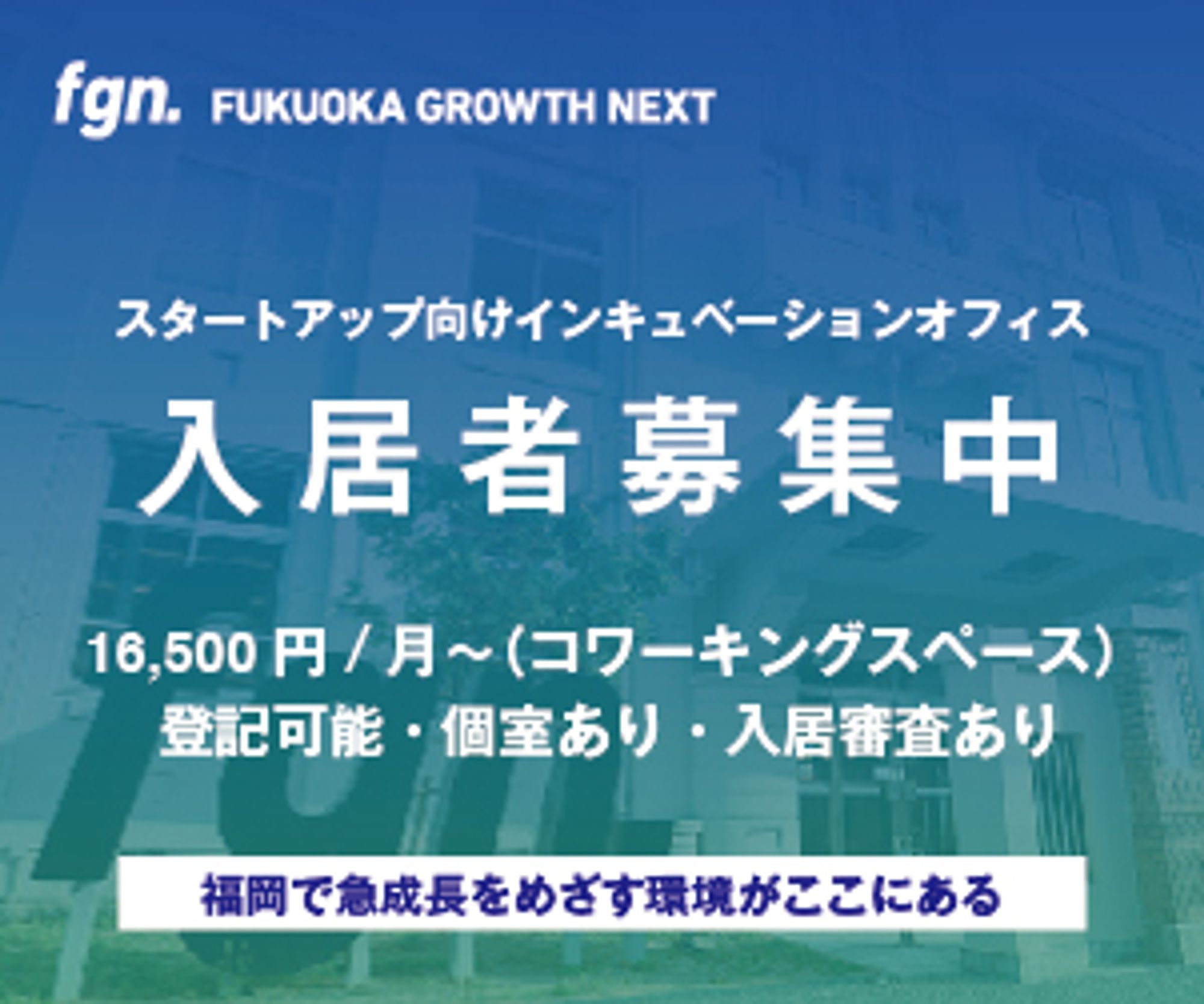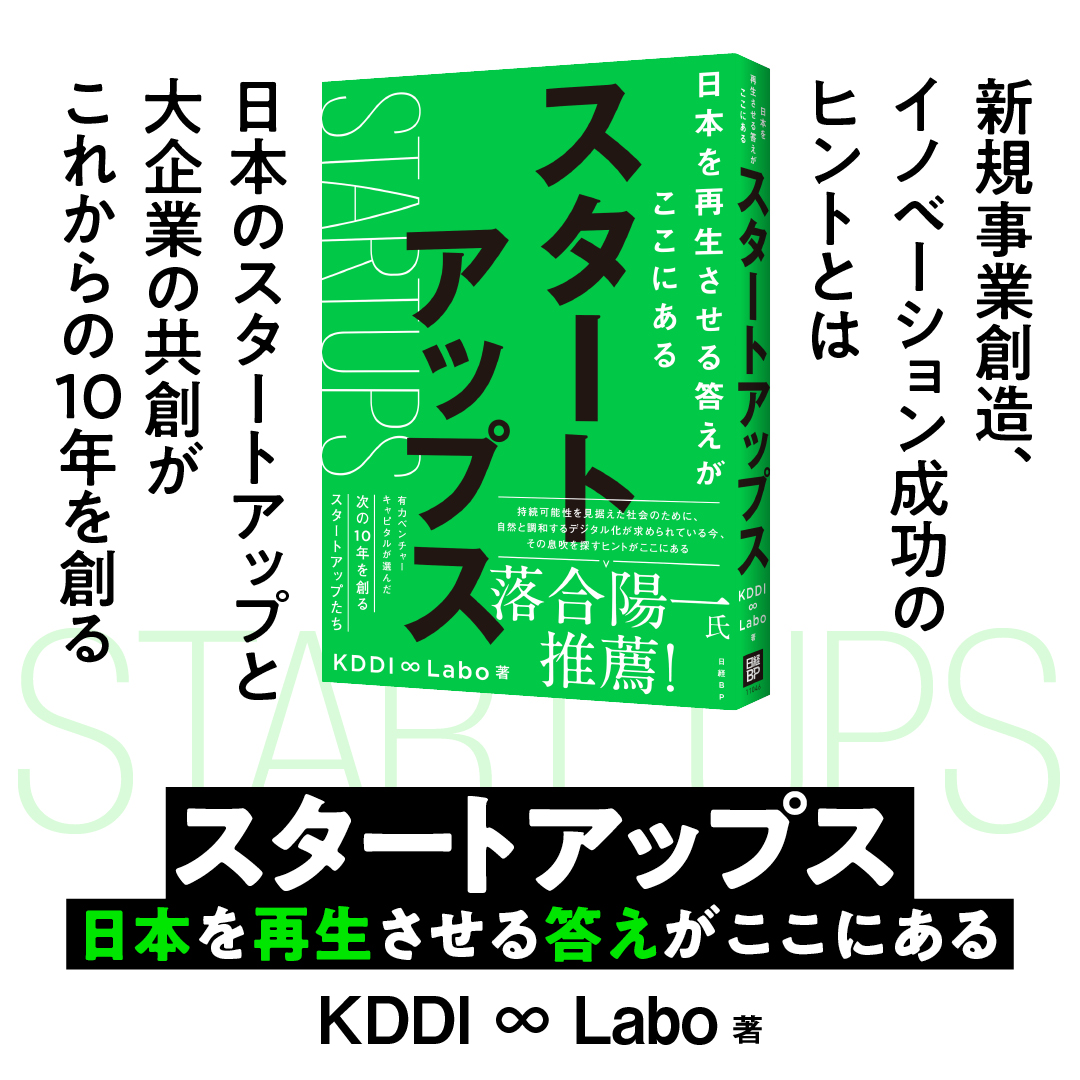わかりやすく流行ってますね、Clubhouse。本誌BRIDGEでも「次期ソーシャル」として音声や常時接続体験についてはいろいろ情報を整理しておりましたが、ここ数日で一気にきた感じです。きっかけはいろいろあるようですが、Andressen Horowitzによる出資が開示されたタイミング(1月25日)と被っているので、その辺りに何かあったのでしょう。Axiosの記事によれば今回ラウンドはポスト評価で10億ドル、1億ドルの資金調達を実施したそうです。
a16zの記事に創業者のPaul Davison氏と共同創業したRohan Seth氏のエピソードが記述されていますが、特にDavison氏、なんとあのHightlightを作った人だったんですね。a16zの出資記事にこう記されています。
「その会社(Hightlight)は最終的にPinterestに売却され、Paulは時間をかけてビジュアル・キュレーションという文脈の中でソーシャル・プロダクトを深く掘り下げていきました。昨年、彼が何か新しいことに取り組んでいると聞いた時、彼に再会できて嬉しかった。それまでに、彼は共同創業者であり友人でもあるRohan Sethとチームを組んでいました。二人は、人々が話したり聞いたりすることがもっと簡単になるよう、音声を使って人々を結びつける新しいプロダクトを開発していたのです。Talkshowと呼ばれるこのサービスは、ユーザーが他のスピーカーを見つけやすくする仕掛けを持っていて、ツールを合理化することでポッドキャスティングをより簡単にすることを目的としていました」(引用要約:Investing in Clubhouse・a16z)。
インターネット老人会な方であれば「FoursquareやGowalla」と聞いてピンとくるはずです。そう、一時期すごく流行った(今もかな)位置ソーシャルの一人でした。残念ながらそれはPinterestにチームとして統合されましたが、その後、再登板を果たしたというわけです。アツい。
国産で常時接続ソーシャルは何がある

前置きが長くなりました。
これだけ一気に広がると冷めるのも早そうな気もしますが、もちろん国産も頑張っています。ちなみに大きなソーシャルの流れとしては(分類は色々ありますが)Facebookなどにある「相互フォロー」からTwitterの「非対称フォロー」、そして現在、DiscordやこのClubhouseにあるような「常時接続」というトレンドがひとつあるかなと思っています。コンテンツもテキストから画像、動画、そして音声、ライブへと変遷するなど、リッチ化が進みました。
古川さん(以降、けんすうと記載します)は例えばClubhouse的な「Yay!(イェイ)」であったり、井口尊仁さんが開発している「Dabel」、音声ライブ配信の「Spoon」、ゲーム配信の「Mirrativ」やバーチャルライブ配信の「REALITY」あたりを挙げられてました。
中でも異彩を放つのがアルの「00:00 Studio(フォーゼロ・スタジオ)」です。彼独自のプロセスエコノミーという考えに基づいて、クリエイターの作ってる間の時間も有効活用しようという常時接続ソーシャルのひとつです。
「(マンガ発見アプリの)アルは漫画界をテクノロジーで良くしたいな、という思いではじめました。実は私がマンガ大好きで、いい作品が増えると自分の人生が豊かになるし、才能あるクリエイターの方々が(経済的な理由から)他の職種に移るのは損失ではないかなと。ということで新人作家さんたちが発見しやすい、そういう場所を作りたいとプロジェクトを開始したのがはじまりです」(けんすうさん)。
新人作家の作品発掘からはじまったプロジェクトは徐々にクリエイターの課題を解決したいという想いに拡大し、「00:00 Studio」の開発に繋がります。けんすうさんはクリエイターが抱える課題として「お金、孤独、ファン獲得」の3つがあると指摘していました。その解決方法として至った考えが「プロセスエコノミー」です。この考え方は以前にも記事にしているのでそちらを参照ください。
- 参考記事:プロセスエコノミーと小さな経済の時代
実際、00:00 Studioを覗いてみると、記事を書いているクリエイター(けんすうさん)は画面の向こうで淡々と記事を書いる様子が生配信されています。ただ、別にその画面をじっと見てるわけではなく、適当に「おはようー」などと声かけをしてくれたり、視聴しているユーザーがコメント蘭にスタンプしたりしてゆるやかにつながる、そういう体験になっています。非常にゆるいです。この辺りは常時接続系のソーシャル特有の雰囲気かもしれません。(テキストでは限界あるので実際に見てみることをおすすめします)。
さて、本題です。常時接続の黒船、Clubhouseが一気に爆発している様子を見て、けんすうさんは何を感じたのでしょうか。特に言及していたのが「モメンタムの作り方」と「編集要素の割り切り」です。
モメンタムについてはもう言うまでもなく、後述しますが、数時間で準備した本記事の公開取材に500人も聴衆が集まるのですから見事としか言いようがありません。これは一度味わうと、次、めんどくさいポッドキャストやろうという気にはなりません。
もう一つが編集の割り切りです。こちらについてはLoco Partners創業者で現在はYouTuberとして活躍されている篠塚孝哉さんのnoteにある記述を引用して説明されてました。
「日本のサービスは編集をしすぎるきらいがある。これは中期には人々を楽しませることができるし、そもそも私もそんな編集が好きなサービスを選びがちだったりする上に大好きである。しかしそれこそがスケールする上での罠である」(引用:日本とアメリカのサービスのスケーラビリティはなんでこんなに違うのか)。
MirrativやREARITYは確かに一部に熱狂的なファンがいることで有名です。しかしこのClubhouseはその「カスタマイズ性」みたいなのを極限にまで削ぎ落として余計なことをさせません。けんすうさんはClubhouseをして、REARTY代表の荒木英士さんの言葉を引用しつつ常時接続ソーシャル界の「らくらくフォン」と表現していました。若者たちしか使えない機能はなく、かつ、インターネット最先端的な雰囲気も味わえる。確かにそうです。老人の私も使えました。
では何が必要か
常時接続ソーシャルが次のトレンドに入るのはもう間違いないと思います。けんすうさんの指摘で気がついたのですが、常時接続の体験に必要な要素に「沈黙」があります。やってみると分かるのですが、間が空くとやや気持ち悪い感じになるんですね。結果、ラジオ的な体験を求めるとずっと喋ってる感じになります。
この黙る、という部分をうまく体験にできかけているのが00:00 Studioではないかと話していました。ちなみに本人もまだ確証があるわけじゃないそうです。実際、お絵描きしている作業の画面をずっと見ているわけでも、コメントし続けるのでもなく、また、配信者は喋り続ける必要もありません。そこにいる人たちが「ただいるだけ」という環境を作り出しているのです。
00:00 StudioはモメンタムこそClubhouseほどではなかったようですが、それでも体験としては非常に独特です。私もできることならこの記事を書いている様子をライブで配信してみたかったです。ちなみにこの記事はClubhouseで公開インタビューしたものを元に作成しました。タイムライン的には次のような感じです。
clubhouse、昨日たまたま立ち話みたいなのに参加させてもらったけど、公開インタビューが一番よさそう。
— kigoyama@BRIDGE・PR TIMES Media (@kigoyama) January 28, 2021
公開インタビューをしようと思いついてTwitterで呼びかけたところ、アルを創業した古川健介さんから「いいよ〜」と快諾いただいたのが午前10時半ぐらい。その後に下記のTwitterを流して、メッセで時間調整、2時半にイベント公開して3時から30分取材という感じでした。
公開取材ひとりめけんすう氏になりました。3時から30分だけ
なんでもやってみよう的な
I'm discussing “【公開取材】アル・けんすう氏に聞く0000 studioって何?”. Today, Jan 28 at 3:00 PM JST on @joinclubhouse. Join us! https://t.co/T2bAMWVJpw
— kigoyama@BRIDGE・PR TIMES Media (@kigoyama) January 28, 2021
このスピード感は確かにらくらくフォンです。新しいフェーズに入った感のあるソーシャル戦争、楽しくなってきました。
訂正:記事初出時にClubhouseの株価について記載しましたが一部修正しておりおます
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待