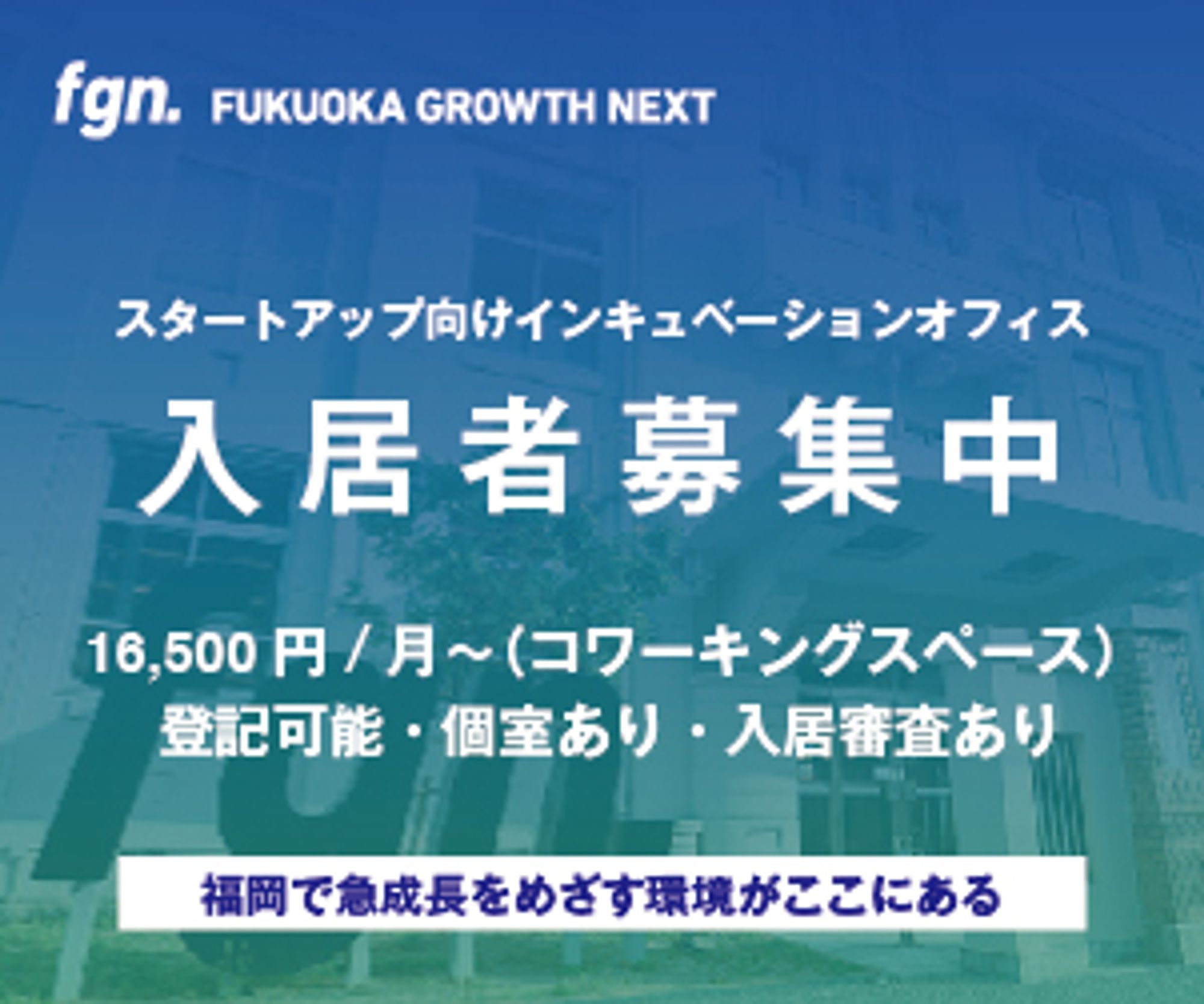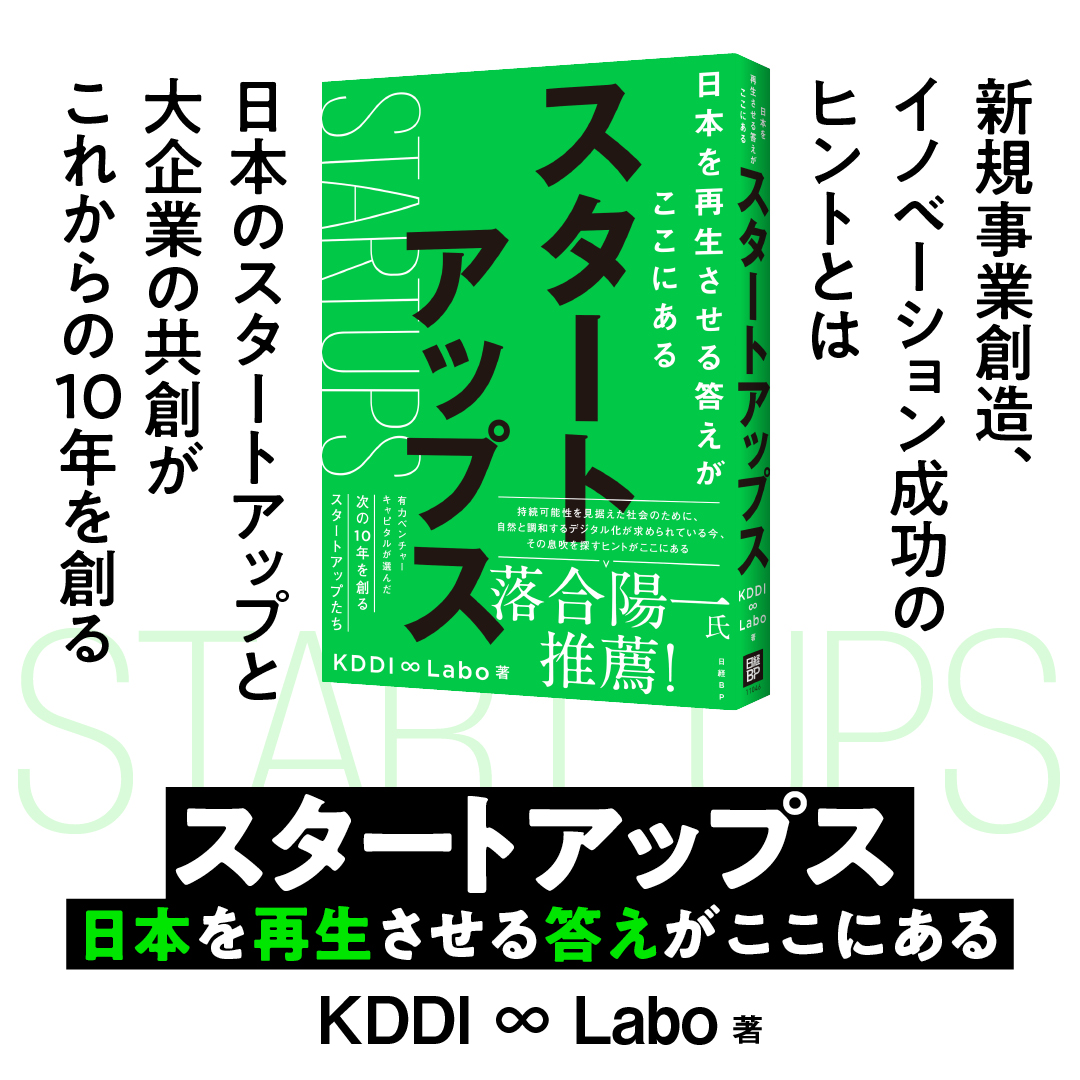Image credit: Masaru Ikeda
和歌山発のバイクメーカー glafit(グラフィット)は2日、日本初の車両区分を変化させられるハイブリッドバイク「GFR」を発表した。GFR はモビチェン(モビリティカテゴリチェンジャー)機構を搭載しているため、原動機(モーター)作動時は原動機付自転車扱い、ペダル走行時は普通自転車として正式に認められ公道を走行することができる。これまでもハイブリッドバイクは存在したが、原動機を作動させず人力で走行させる場合であっても原動機付自転車として扱われ、適用される交通法規に従う必要があった。

Image credit: Masaru Ikeda
ハイブリッド自転車がペダル走行時にも原動機付自転車扱いとなるのは、交通法規上、原動機の作動如何にかかわらず、そのモビリティが持つ最高性能に合わせた法律が適用されるべき、という法的解釈によるためだ。しかし、日本の道路は、車道と自転車および歩行者専用道路にのみ大別されていて、小型モビリティのための道路区分は存在しない。大型自動車が多く走る高い最高速度が設定された道路においても、原動機付の小型モビリティは自転車および歩行者専用道路ではなく、車道を走る必要があった。
glafit は内閣官房日本経済再生総合事務局(現・成長戦略会議事務局)のサポートを受け、和歌山市に規制のサンドボックス制度に共同申請。2019年11月から実施してきた実証実験を経てモビチェン機構を開発し、警察庁での最終確認を経て、1台の車両で電動バイクと自転車の切替を認める通達が出された。この道路交通法上の解釈変更により、モビチェン機構を搭載した GFR は今後日本国内で、運転状態に応じて、原動機付自転車、または、普通自転車として扱われることになる。

glafit が開発したモビチェン機構はハイブリッドバイクの後部に搭載され、原動機が作動している際には自動車ナンバーが、また、原動機が作動していない際には自動車ナンバーがマスクされ自転車のシンボルマークが表示されている。原動機を作動させる電源と連携させているため、運転状態が担保される仕組みだ。glafit ではモビチェン機構が、ドローンと自動車、電動バイクと電動アシスト自転車など、モビリティの運転状態の変化に応じて、柔軟な交通法規を適用させる仕組みとして期待したいとしている。
glafit は2017年9月の設立。代表取締役の鳴海禎造氏は和歌山市内で2003年から FINE TRADING JAPAN (RM Garage という屋号で個人事業として創業)、四輪車や二輪車のドレスアップ・パーツの製造や販売を行ってきたが、代表取締役の鳴海禎造氏が、ベンチャーの先駆け的存在でもあるフォーバル(東証:8275)創業者の大久保秀夫氏に出会い、今必要とされるモノを作るだけでなく、100年のビジョンを持って会社を経営すべきと諭され、モビリティ分野にパラダイムシフトを起こすべく glafit を開発した。

同社はこれまでに、マクアケ、オートバックス、ヤマハ発動機、パナソニックなどと協業、また、立ち乗り電動バイク「X-Scooter LOM」、電動ハイブリッドバイク「glafit」などを開発している。モビリティの啓蒙活動にも注力し、日本電動モビリティ推進協会を組織して鳴海氏が代表を務めている。モビチェン機構を装着した GFR-02 の走行が始まるにあたり、同社では警視庁や全国の府県警察本部に試乗キャラバンを伴う普及活動を実施する計画だ。
BRIDGE Members
BRIDGEでは会員制度の「Members」を運営しています。登録いただくと会員限定の記事が毎月3本まで読めるほか、Discordの招待リンクをお送りしています。登録は無料で、有料会員の方は会員限定記事が全て読めるようになります(初回登録時1週間無料)。- 会員限定記事・毎月3本
- コミュニティDiscord招待