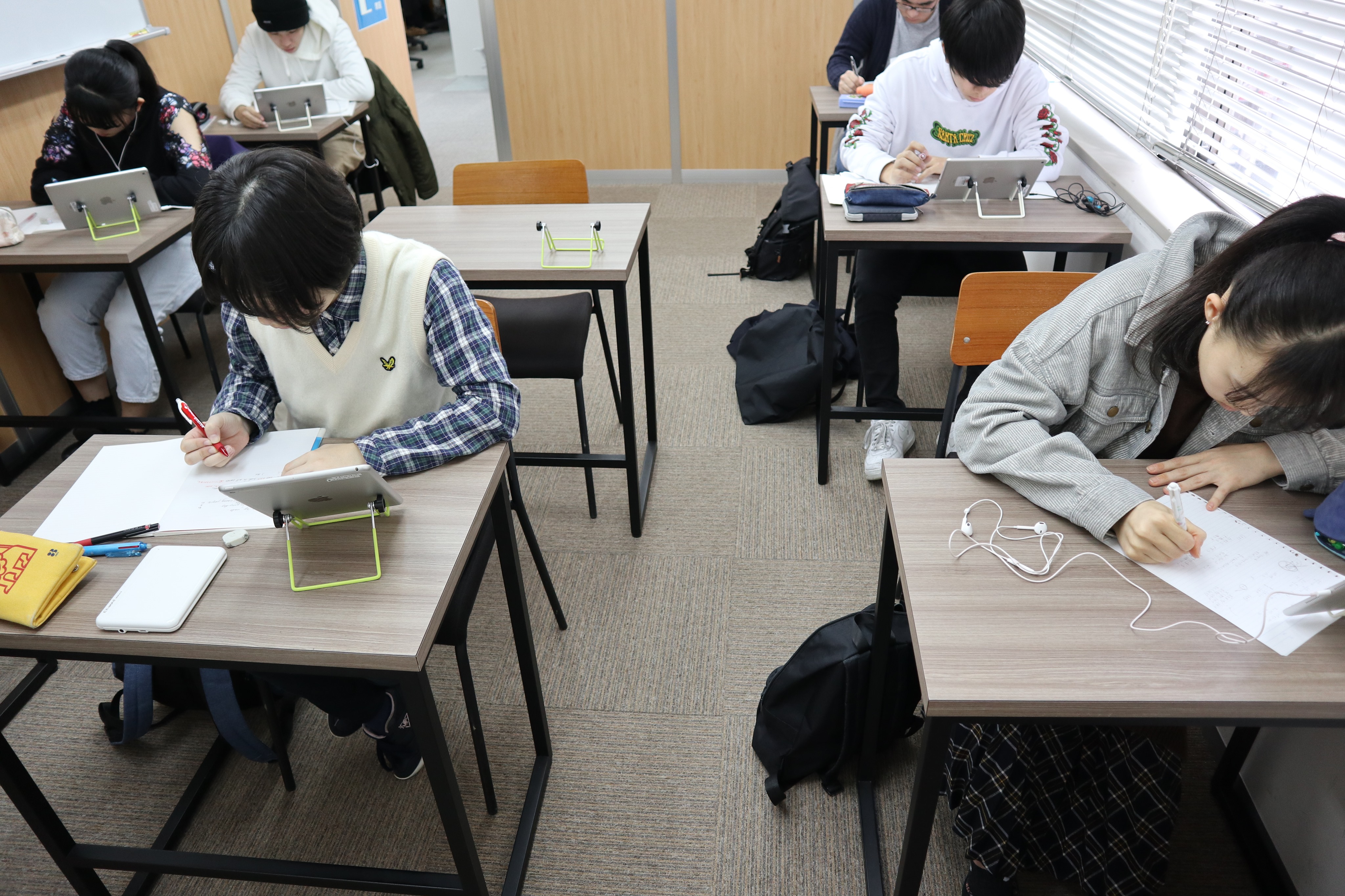ニュースサマリー:米Amazonは25日、同社初となるキャッシャーレススーパーマーケット「AmazonGo Grocery」をシアトル市街にオープンしたことを発表した。無人店舗の仕組みは同社が2018年1月に一般に公開した無人コンビニ「Amazon Go」と同じものを利用。そのため、入店の際はAmazon GoアプリよりQRコードを認識させることで入店できる。
店舗には肉や魚の生鮮食品などAmazon Goでは取り扱いが少なかった商品も取りそろえる。また、商品入れ替えのためスタッフはAmazon Go同様に常駐するという。
話題のポイント:2020年に入り、AmazonがAmazon GoやWhole Foodsを起点としたOMO戦略を進めていく報道が度々されていました。なかでもAmazon Goは、店舗数拡大の一手として空港をターゲットにした戦略をとるといわれ、データのタッチポイントを格段に増やす段階に入る年となるのでは、とされていました。
<関連記事>
しかし蓋を開けてみたら、Amazonの取った2020年の初手はAmazon Goを拡張したスーパーマーケット「Amazon Go Grocery」でした。取扱商品は格段にバラエティーが広くなり、アルコールや生鮮食品も見受けられ、利便性が大いに高くなったことは間違いありません。

1時間まで無料の駐車場が併設されていることや営業時間が日曜日から木曜日は23時まで、金土は深夜0時までと、米国のスーパーマーケットとしては夜遅くまで対応していることが特徴です。
ただ、まさにAmazon Goを「大きくしただけ」という表現で全て説明できてしまうように、無人コンビニの”利用体験”における変化はそこまで見受けられないと感じました。上述したように、基本的なテクノロジーはAmazon Goのものがそのまま利用されているため、以前からの利用者であれば体験に特段変化が無いのは当然です。

さて、筆者はオープン初日に訪問したこともあり、客層はいわゆるテック系やメディア関係者が多いと予想していました。しかし、実際は驚くことに30代から60代までの幅広い家族・老夫婦がとても多いという印象を受けました。
店舗の所在地は、まさに住宅街の中心でダウンタウンから数十分の場所にあり30代の家族が多く見受けられるエリアなのですが、病院施設が多く構えているエリアでもあり多種多様な層の「通り道」であることが特徴です。敢えてダウンタウン中心ではなく、30-60代が自然と集まりやすく、それなりに裕福な層が多いからこそ出店場所として最適と判断したのかもしれません。

下図の左上に見えるのが、Amazon Go Groceryのロケーションです。そこを起点に南下すると、Amazon GoとWhole Foodsまでもが点在しています。そのため、この周辺に住居を構えていると必然的に3店舗のうちのどれかを利用することになり、いずれの場合でもアマゾンとタッチポイントが生まれる仕組みとなっています。

ただ、Amazon Go Groceryは少なくとも現在は「Amazon Go拡張版」であり購買体験は特にアップデートされているわけではありません。加えて、Amazon Go Groceryで取り扱う商品は限りなくWhole Foodsでも購入可能なものがほとんどなのが現状です。(GroceryではWhole Foodsブランドの商品も取り扱う)
そのため、各ブランドの線引きが曖昧となってしまう印象を受け、またGroceryもスーパーマーケットとしては大きいといえず、スーパーマーケットとしての満足度も中途半端な存在となってしまうことが危惧されます。

とはいえ、明らかにAmazon Goと比較すればローカル住民が利用する理由として利便性の面では最適化されたことには間違いありません。Amazonが申請した特許に「手のひらPay」があることを以前報じましたが、こういった観点を組み合わせ今後体験のアップデートが実施される可能性は大きくあると思います。
筆者の考えとして、Prime会員であれば無料配達をしてくれるWhole Foodsがアマゾン会員の恩恵として最大の価値だと感じているのですが、今後アマゾンが「Amazon Go / Amazon Go Grocery」を利用する理由を提示してくれることを楽しみにしています。
Members
BRIDGEの会員制度「Members」に登録いただくと無料で会員限定の記事が毎月10本までお読みいただけます。また、有料の「Members Plus」の方は記事が全て読めるほか、BRIDGE HOT 100などのコンテンツや会員限定のオンラインイベントにご参加いただけます。無料で登録する